中国語語学誌『聴く中国語』は毎月、日本で活躍している中国の有名人や日中友好に貢献している日本人にインタビューをしています。
今回は、今年出版された「闇の中国語入門」が話題のサブカルチャー専門学者・楊駿驍さんにインタビューしました。来日後のご苦労からサブカルチャーを研究するに至った経緯、現在行われている活動などについてたっぷり伺いました!
――簡単に自己紹介していただけますか?
こんにちは。楊駿驍と申します。私は1990年に中国の吉林省吉林市で生まれ、2013年、13歳の頃に日本に来ました。中学、高校、大学、そして修士・博士課程までずっと日本で学び、現在は二松学舎大学で講師をしています。
日本に来たばかりの時は日本語が全く話せませんでした。当時、周りに中国人も少なく、学校に一人だけ中国人がいましたが、私と同じ学年ではありませんでした。突然日本人の中に放り込まれた環境で、中学3年生になるまで日本語をうまく話せず、日本の学生と友達関係を築くのも難しかったです。非常に困難な時期を過ごしました。しかし、2年ほど経って、突然日本語が話せるようになりました。段階的に上達したわけではなく、ある日突然話せるようになったのです。その後、日本の同級生との関係も少しずつ良くなりました。
そして高校に進学しました。私の高校は神奈川総合高等学校で、県内在住の外国人入学特別枠がありました。また、自分で考える力を養う教育環境があり、寛容な学校でした。もしこの高校に入学していなかったら、今の私はいなかったかもしれません。

その後、早稲田大学に進学しました。当初は心理学を学びたいと思っていたので、心理学科のある早稲田大学文学部に入学しましたが、入学後、文学の方が面白いと感じ、英米文学科に進みました。しかし、学部時代に私が研究したのはアメリカで英語で執筆している中華系作家の作品で、研究するうちに、中国に対する興味が湧いてきました。自分自身も中国で生まれ育ち、中国系作家たちと立場が似ていると感じたため、修士課程からは中国について研究することを決め、現在までその研究を続けています。

――いつからご自身のアイデンティティについて考えるようになりましたか?
中学時代の経験はとても辛いものでした。いじめを受け、「死ね、中国人」と言われることもありました。そのため、自分が中国人であるという身分を否定したくなり、特に周りに自分を中国人としてではなく、一人の人間として認めて欲しいと思うようになりました。周りが思う中国人としての行動の枠を超えて、中国人という身分から抜け出したいと思いました。しかし、大学に進学してからは、先ほど話したように、中国がとても面白いと感じるようになりました。

――修士、博士課程の研究テーマは何でしたか?
修士課程では、サブカルチャー、特にメディアを中心としたサブカルチャーを研究しました。例えば、2000年代末から2010年代初頭に流行した「微映画」という動画形式です。この形式は、現在非常に人気のあるショート動画や抖音(TikTok)の前身とも言えます。なぜインターネット時代に、中国のようなインターネット環境で、このような形式が出現したのかを研究しました。
博士課程では研究の領域をさらに広げました。中国2000年代以降、いわゆる「80後(80年から89年生まれ)」世代が見た世界、この世代の人々がショート動画や哔哩哔哩(Bilibili)などのプラットフォームを通じてどのように自己表現をし、新たに別の世界を想像するのかについて研究しました。

当時の中国では、現実社会のさまざまなプレッシャー、例えば大学入試(高考)や社会での競争のプレッシャーがあり、中国の若者たちは現実のプレッシャーから逃れ、自分自身を自由に発揮でき、自分が認められる場所を求めていました。そんなとき、インターネット空間は非常に重要な、まるでユートピアのような存在になったのです。
2014年ごろ、中国のインターネット上に「弾幕」という機能が導入されました。この機能は日本から中国に導入された後、中国では日本よりもさらに大きな支持を得ました。映画、オンライン講義、音楽鑑賞、ネット小説、ネット漫画など、あらゆる場所に弾幕が存在します。「弾幕」という機能の文化的な意味を詳しく観察すると、元の作品を批判することによって「解体」することだとわかります。
例えば、『還珠格格』で爾康(皇女紫薇の夫)が非常に感動的なセリフを言う場面で、弾幕で「彼の鼻の穴は本当に大きい」と書かれていました。その弾幕で、作品全体の印象が完全に変わってしまいます。これは、解釈の権利を普通の観客に与える革命的な機能です。この「弾幕」は私たちのコミュニケーションにおいて、当たり前のように、どこにも存在するようになる時点、私たちの世界に対する想像の仕方、世界との関わり方にも影響を及ぼされます。かつては揺るぎないと思われていた規範やルール、常識が、実は解体可能であり、そこから抜け出すことができることに気づかされます。

『三体』が中国でこれほど人気を集めたのはなぜでしょうか?80年代生まれのSFファンが『三体』を好きなのは、この小説が「現実の必然性」を相対化する作品だからです。
(『三体』には)「農場主」と「射撃手」の寓話があります。農場主は毎日決まった時間に七面鳥に餌を与えます。七面鳥の科学者は、我々の宇宙はこのように、毎日10時に食べ物が降ってくるのだと言います。しかし、その日、農場主は復活祭のため、七面鳥を殺すことに決めたのです。つまり、確固たる現実そのものが非常に偶然であり、ある「超越的な主体」によって随意に決定されているかもしれないことを示しています。私たちが法則だと思っているものは、誰かの突発的な思いつきであるかもしれません。
この寓話が教えてくれたのは、現在人類が見えているものや経験しているもの、一見して非常に正常で当然だと思われるものが、実は正常でも当然でもなく、変えることができるものであり、非常に偶然なきっかけによって完全に変わることもあるということ。この「変わる」ことは、前の世代の人にとっては「危険」です。なぜなら社会の流動性と不確実性が大きい(というのは彼らにとって危険である)からです。しかし、若い世代にとっては、これがチャンスとなり得ます。

弾幕が流行した時期と中国のSFが流行した時期は重なっています。SFは科学技術を通じて現実を想像し、解体するものです。こうした「文化感性」は、弾幕のような俗なものから文学のような雅なものまで貫いています。言論統制が最も厳しい時代であっても、このような感性は常に存在していました。
(しかし今、解体的な解釈も統一化されつつあります。)そうです。これは物事の両面性を示しています。自分がある規範から抜け出したと思っても、別の規範に取り込まれていることがあります(郝景芳『生于1984』)。しかし、この両面性に気づくこと自体も重要です。自分が本当に自由であるかどうかを常に疑ったほうがいいということです。
――楊さんの思想形成に深い影響を与えた作品は何ですか?
学部時代に最も好きだった作品はフィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』です。(どうしてですか?)この小説は、理想や夢のような一見輝かしいものの裏側に、非常に世俗的で、個人的で、欲望的なものが存在していることを露わにしており、この対照性を映し出した作品です。この小説を読むことでしか感じられない世界に対する認識があります。それは、「自分が高みに達したと思う時、実際にはすでに泥土に落ちている」ということです。(それから矛盾性のある問題に関心を持つようになったのですか?)そうです。私は矛盾や対立に興味があります。(それは研究にも反映されていますか?)はい。
――今年出版された『闇の中国語入門』と『日中間ゲーム文化論』についてご紹介いただけますか?
まず、『日中韓のゲーム文化論』についてですが、この本は以前、中国の大陸で出版された『日本ゲーム批評文選』が原型です。この書籍が中国では出版され、日本では未だに出版されていないというのは非常に奇妙な状況です。中国や韓国のゲーム業界は、その存在感が非常に大きくなっています。例えば、『原神』のようなゲームや、韓国のオンラインゲームは、日本でも多くのプレイヤーがいます。しかし、日本でのゲームに関する批評や評論、認知は、日本と欧米の視点に偏っており、中国や韓国を完全に無視しています。
この本を編集した目的の1つは、中国や韓国のゲームがどのような社会的背景の中で登場し、どのように発展してきたのか、そして学者たちがゲームについてどのように語り、考えているのかを説明することです。ゲームというメディアの別の可能性を真剣に考え、日本やアメリカとは異なる視点でゲームの可能性を理解することができるのです。
――中国、日本、韓国のゲーム文化における明らかな違いは何だと思いますか?
中国のゲーム文化で特に顕著なのは、競争を重視している点です。競技系のゲームが非常に多く、これは中国の「競争社会」という背景に関連しています。韓国も同様です。
一方、日本ではシングルプレイヤーゲームが主流で、PlayStationや任天堂のゲーム機を購入して家でプレイします。しかし、中国や韓国ではインターネットカフェに行って、知らない人と一緒にプレイすることが一般的です。これは日本とは大きく異なる点で、非常にソーシャルなゲーム文化です。 日本の読者の皆さんに、ゲームには多くの可能性があり、異なる社会で異なる機能を果たすことがあるということに気づいていただけたら嬉しいです。

――もう一冊(『闇の中国語入門』)はいかがでしょうか?
もう一冊の本についてですが、出発点は単純です。暮らしを立てるために、大学で中国語を教える必要があったとき、私の先生が取り置いていた全ての中国語の教科書を私の家に送ってくれました。それを一冊一冊、私の妻(中国語教育に携わる段書暁さん)と一緒に見ました。見ていくうちに、違和感を感じるようになりました。「これらの本はどうしてどれもこんなに似ていて、同じような世界観が描かれているのか。どうして登場人物はみんな仲良く、親しい関係を築き、生活がこんなにも美しく描かれているのか?」という疑問が浮かびました。
この点に気づいたとき、言語学そのものも「批評」の対象になり得るのではないかと思いました。それで、オンラインプラットフォーム「note」で「黒暗中国語」という連載を始めました。毎回一つの単語について書くというもので、それがこの本の原型となりました。その後、筑摩書房の編集者がこの内容を見て、本書の企画が始まりました。
非常に重要な点は、大学で使われる外国語教科書というメディア自体がマスメディア(Mass Media)であるということです。マスメディアが一つの世界観だけを伝えることは、非常に病的なことです。したがって、この本は一方では中国語教育に対する批評であり、もう一方では外国語教育というマスメディア自体に対する批評でもあるのです。
さらに、これまで語学教育と文化・文学の教育は分けられてきました。語学は語学、文学は文学というように。しかし、私たちが言語を使用する際には、これら二つを完全に分けることはできません。ですので、この本は中国語の語彙を解釈することで、中国現代文化を紹介するという、これまで分けられていた二つの要素を再統合しようとする試みでもあります。

――中国の現代文化や若者の思想状況にはどのような興味深い特徴があると考えますか?日本の若者とどのように異なりますか?
違いについてお話ししましょう。『闇の中国語入門』でも触れたように、中国の若者は自分の負の感情やあまり良くない経験を共有し、他人との感情的なつながりを築こうとする傾向があります。
一方、日本の若者は、友人との関係を維持するために、できるだけマイナスなことを言わず、自分の弱さやネガティブの気分を表に出さないようにします。楽しい瞬間や経験を共有することはありますが、相手が感情的に困難で苦しい状況にあるときに助けるのは難しいのです。これは私が気づいた割とわかりやすい違いです。ですので、この本を通して、負の感情によって人とより深くつながることができるということに読者に気づいてもらえたらと思っています。
――中日文化のカルチャーショックに関して、特に興味深い出来事や忘れられない出来事はありますか?
最も忘れられないのは、中学生の頃のことです。当時、弁当を持参する必要がありましたが、両親は日本の弁当がどういうものか知らなかったため、餃子やさまざまな中華料理を持たせてくれました。ところが匂いが非常に強く、教室で皆が私のお弁当の強烈な匂いを我慢しなければならず、これが原因で、私は学校で非常に苦しい立場に置かれました。
日本の文化では「空気を読む」ことが強調されており、最も物質的な「空気」が匂いです。私が外国人で、彼らがその匂いを耐えられないということを理解することができず、また精神面においても、私は彼らの「空気」を「読む」ことができなかったため、「この中国人は迷惑だ」という「空気」が生まれてしまいました。その結果、「死ね、中国人」と言われたり、完全に無視されたりしました。まるで私が存在しないかのように、話しかけられなくなりました。日本のいじめの陰湿さは、皆の交流の輪から排除するという点にあります。物質的な攻撃や言葉による攻撃ではなく、完全に排除するのです。
――その後、この状況をどのように克服したのでしょうか?
「異物性」を発揮することで、逆に承認を得られるようになったのです。私は中学三年生の頃には日本語が上達し、わけのわからないジョークを言うようになりました。彼らはそれを面白いと感じ、私の「異物性」を受け入れてくれるようになりました。彼らにとって、私がおかしな人であることに変わりはありませんが、以前は嫌われていた「おかしさ」が面白いと思われるようになったのです。
――楊さんと奥様は定期的にオンラインでトークイベントを企画されているそうですね。このイベントについてご紹介いただけますか?
このイベントは、非営利法人「NPO星光(ほしのひかり)」が主催しています。多くの方が一緒に携わっています。(妻が副理事長で、私は理事を務めています)妻は(イベントで)司会を担当します。 私たちは一緒に企画を行って、毎回、特定の業界で活躍しているトップランナーをゲストとしてお招きしています。例えばシェフやファッション研究者、セクシュアリティの指導者などをお呼びして、日本の華人コミュニティで宣伝を行っています。

――楊さんと奥様がこの活動を始めた初心は何だったのでしょうか?どのような収穫がありましたか?
私たちがこの活動を始めたのは、普段接する人とは異なる人々の経験や知識を共有することで、私たちの世界を広げたいとの思いからです。文化活動に触れる習慣がなかったり、言語能力が不足していたりすると、文化的な生活の範囲が非常に狭くなってしまいます。
ゲストの方たちと接したり、話を聞いたりすることで、新しい見解や生活、人生、社会についての新たな知識を得ることができます。これらの知識は書物では得られないものです。
(招待するゲストは基本的に華人ですか?)日本人のゲストもいます。例えば、以前に吉井忍先生を招いたことがあります。吉井忍先生は日本人ですが、中国ではベストセラー作家です。私が吉井忍先生と一緒に行った対談イベントは、私たちが初めて日本語で開催したイベントで、多くの日本のお客様が参加しました。このような日本語のイベントは、日本にいながらも中国に関連する知的な内容に触れられる空間を提供しています。
――最後に、読者の皆さんに言語学習の経験や心得をシェアしていただけますか?
言語学習についてですが、私自身も中国語を教えているので、言語は生活や経験、文化、社会と切り離せないものであるということをお伝えしたいです。単なるスキルとして言語を学ぼうとすると、大きな確率で失敗してしまうでしょう。私の学生にも言っていることですが、自分が興味を持てることや対象を見つけ、それを中心に言語を学ぶことで、継続することができます。たとえ途中で興味の対象が変わっても構いません。継続することができます。私自身の経験もそうでした。ゲームや小説が好きだったので、英語や日本語を学ぶ際には、そういった自分が興味のある、興味を持てる作品を中心に学びました。これは今の私の研究の原動力にもなっています。私のアドバイスは、趣味を持つこと、興味のある事を見つけることです。
――ありがとうございました!

楊 駿驍(よう・しゅんぎょう)
1990年中国吉林省生まれ。日本育ちの満州族。早稲田大学文学部卒業。同大学文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(DC2)、早稲田大学文学部講師を経て、現在、二松学舎大学文学部専任講師。専門は現代中国文学とサブカルチャー。中国語、コミュニケーション学、ゲーム文化論の授業を担当。総合批評誌『ヱクリヲ』や中国の人文系メディアで、思想、ゲーム、SF、デザイン、マンガやアニメなどに関する論考を執筆。著書に『闇の中国語入門』(筑摩書房)、『日中韓のゲーム文化論』(共編集 新曜社)がある。
今回のインタビュー内容は月刊中国語学習誌『聴く中国語』2024年11月号に掲載されています。さらに詳しくチェックしてみたい方は、ぜひ『聴く中国語』2024年11月号をご覧ください。

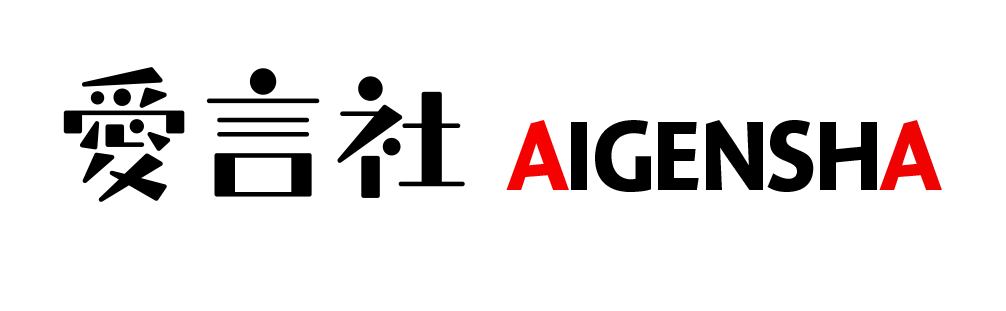



コメント