中国語語学誌『聴く中国語』は毎月、日本で活躍している中国の有名人や日中友好に貢献している日本人にインタビューをしています。
今回は日本華僑華人文学芸術界連合会会長であり、著名な揚琴演奏家でいらっしゃる郭敏先生にインタビューしました。先生と揚琴の物語を聞いてみましょう。
――先生はどのように揚琴と出会い、どのように揚琴演奏家の道を歩むことになったのでしょうか?
実は揚琴は両親から学ぶように言われました。父はバイオリンを弾くことができました。軍人でしたが、なぜかバイオリンを持っていたのです。趣味だったんですね。思い返すと、父はとても不思議な人でした。私は9歳か10歳くらいから揚琴を学び始めました。 当時はオーケストラに入ろうとしましたので、私は「星海音楽学院」を受験しました。もともとは音楽学院に入るつもりでしたが、ちょうど広州オーケストラが急遽人材を募集していたのです。広州オーケストラは中国の三大オーケストラの一つです。中央、上海、広州は当時の三大オーケストラでした。それで私は急いで応募して、無事入ったのです。当時、十代でした。そのようなことで、音楽学院には進学しませんでした。中断したとも言えます。

――それから、どのようなきっかけで日本にいらっしゃったのですか?
当時、中央音楽学院の院長で、中国音楽家協会の会長だった方が、公演の際に私に目をつけてくださり、中央音楽学院に呼んでくださったのです。私はとても嬉しくて、行こうと思いました。しかし、オーケストラ団内で同意されませんでした。私は頭にきて、「北京がだめなら、東京に行ってやる」と考えたのです。当時、留学することは誰も止めることができませんでしたから。でも、それでも1年間足止めされました。(謝:団はあなたが離れることを望んでいなかったのですね。)そうです。仕事でも必要とされており、当時ちょうど2つの賞も取っていて、「賞を受賞した演奏者は国外に行ってはいけない」と言われました。とにかく、私を離れさせたくなかったのです。

――日本に来たのは90年代ですか?
87年です。当時、中国の音楽は非常に人気がありました。中国音楽だけでなく、中国の各分野が注目を集めていて、「中国ブーム」でした。中国のものを買ったり、中国のものを食べたり、中国の音楽を聴いたり、中国語を学んだりというように。それに、各地に日中友好協会がたくさんありましたから、私たちにとってはすばらしい時代でした。私たちはそのような日中関係が親密な時期に日本にやって来て、日本人も私たちに対してとても親切でした。

――揚琴の魅力をご紹介いただけますか?
実は、揚琴は海外から来たもので、中国の楽器ではないんです。(もともとは)アラビアから伝わって来た、サントゥールという名の楽器です。(かつては洋琴や蝶琴と呼ばれていたが、60年代に楊琴に統一された。)このサントゥールは、西に伝わってピアノに変わり(ダルシマー、ツィンバロム、クラヴィコードも同様)、東に伝わって揚琴に変わったのです。ですから、(揚琴は)東アジアや東南アジアの多くの国で見られます。
この楽器の魅力の一つは、弦を打つこと、弦をたたくことです。日本には「打弦楽器協会」というものがあります。打弦楽器は揚琴とピアノしかありません。揚琴は直接弾くのに対して、ピアノは間接的で、手は鍵盤を押さえますが、実際には後ろで弦をたたいています。ピアノの後ろを見れば分かりますね。(揚琴は)非常にシンプルで、ピアノのように打つだけでいいんです。でも難しいのは、ピアノは専門の人が調律をしますが、揚琴は自分で調律をしなければならないということです。

――先生の代表作をいくつかご紹介いただけませんか?
たくさんありますよ(笑)。「彩雲追月」と「柳浪聞鶯」、「昭君怨」、これらは全て(原本は)合奏曲で、(私が)それを揚琴の独奏曲に改編しました。多くの名曲は揚琴の曲にアレンジすることができます。
あともう一つは、みなさんがよくご存じの「梁山泊与祝英台」です。中国人はみんな知っているかもしれませんね。これはバイオリンの協奏曲です。私は揚琴を使って、このバイオリンのバージョンを(揚琴を使った独奏曲として改編して)演奏します。

――読者の皆さんに言語学習に関するアドバイスをいただけますか?
私自身、学校での勉強のほかに、まずは、会社へ戻ると日本人になりきることですね。これはとても大事です。環境は大事だと思います。例えば読者の皆さんが日本人で中国語を学びたいのであれば、できるだけ中国人と接するほうがいいでしょう。もしこの環境がない場合は、なんとかしてその環境つくるんです。今は、テレビなど、そうした(手段が)充実していますしね。

私は来日後、中国語の番組を聴きたくて、短波ラジオ放送を聴ける(レコーダー)を探しました。子供に聴かせたいと思いましたが、あまりうまくいきませんでしたが(笑)。子供に中国語の環境を作りたかったのです。私も小さい頃そうでしたから。私は広東で育ちましたが、広東の人は国語があまり得意ではありません。父は毎日私がまだ寝ているのに、朝っぱらから「中央人民放送局」のラジオを大音量で流していて、私は夢の中で国語を聴いていました。私の標準語はこのように耳を通して、知らず知らずのうちに身に付いたのです。ですので、中国人と話すことができなくても、ラジオをずっと流していれば、自然と耳に入っていくのです。
もう一つはテレビを見ることですね。私は日本に来たばかりの頃、サスペンスを見るのが好きでした。火曜日、金曜日、木曜日のサスペンスはすべて見ました(笑)。サスペンスは全国(で撮影した)番組ですので、各地の風習や風景を見ることができ、さらに日本語を勉強することもできるのです。(謝:環境も趣味も大切ですね。)最近日本にやって来た友人がどうやって学べばいいかと言うので、「サスペンスを見てみて」と言いました(笑)。
――ありがとうございました!
ありがとうございました。

郭敏
中国広州生まれ。中国音楽家協会会員。国際ツィンバロム協会会員。日本打弦楽器協会会員。星海音楽学院にて、本格的な音楽教育を受け、系統的な揚琴(南派)の奏法を学ぶ。広東民族楽団に入団以来、ソリストとして活躍。『全国民族楽器ソロコンクール』で優勝、 『羊城音楽コンクール』ほか数々のコンクールで入賞し一躍注目を集める。
1987年来日。全国各地でソロコンサートを行う傍ら、89年より東京芸術大学音楽学部で民族音楽を学ぶ。
NHK「花の舞台」「名曲アルバム」「スタジオパーク」などのテレビ出演、CD、映画音楽(『チャイナシャドー』『金田一少年の事件簿』『墨攻』)、 CM音楽(ライオン、JR東日本など)等で幅広く活躍する傍ら、日本、韓国、アメリカ、アフリカなど世界各国のミュージシャンと共演し、揚琴音楽の新しい世界を切り開いている。
(主な出演歴)
文化庁芸術祭出演・『PACIFIC MUSIC FESTIVAL』『ISSEY MIYAKE パリコレクション』『平安京1200年記念式典(天皇陛下御臨席)』
TOKYO-FM主催・文化庁後援『シルクロード音夢紀行』(TOKYO-FMにて3日間にわたり放送)
新星日本交響楽団主催『揚琴の伝統と現代』(旧東京音楽学校奏楽堂)
アジア作曲家連盟主催『アジア音楽祭in横浜』
今回のインタビュー内容は月刊中国語学習誌『聴く中国語』2024年4月号に掲載されています。さらに詳しくチェックしてみたい方は、ぜひ『聴く中国語』2024年4月号をご覧ください。

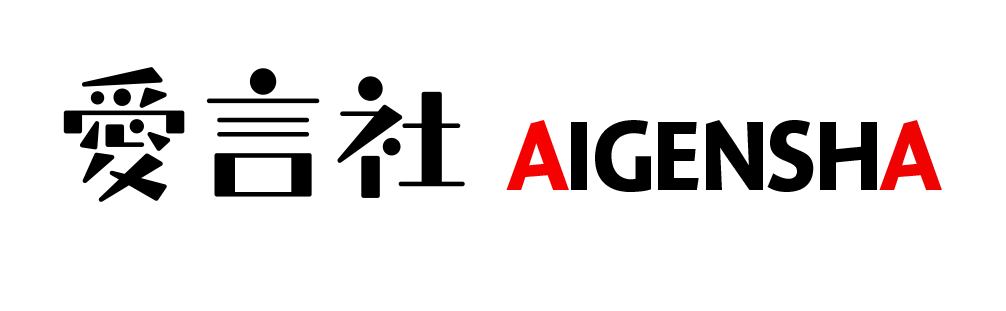



コメント