最近、ニュータイプの茶系飲料ブランドが続々とお目見えしている。その中には、日本の若い世代にもよく知られたゴンチャ(Gong cha)、THE ALLEY ジアレイ(鹿角巷)、HEYTEA(喜茶)などがある。ニュータイプの茶系飲料とは、単に「タピオカミルクティー」だけを指すのでは決してなく、伝統茶に革新的なアレンジを加え、消費者が全く新しいティードリンクを味わえるようなものを指す。ニュータイプの茶系飲料は、原料やトッピング、味や食感、作り方、パッケージやネーミング、さらには消費者に浸透していくルートに至るまで、全てにおいて新しさがある。今回の大接近では、近年中国で登場した独特で美味しい「新・茶系飲料」を見ていこう。


台湾タピオカミルクティー(1980~90年代)
1980~90年代、台湾でタピオカミルクティーが登場すると、瞬く間に台湾海峡の両岸で大人気になり、ひところはミルクティーを売る店が街のいたるところにあふれた。


ミルクティーの主原料はお茶と牛乳ではあるものの、ミレニアム前後の中国大陸では、粉末にお湯を注いで作るミルクティーが大半を占めていた。健康面の問題はいったんさておき、少なくとも若者たちは、数元という安さで、流行りの美味しいミルクティー系飲料を飲むことができた。

1點點
2011年、台湾の「1點點」が上海に進出し、他店に先駆けて「淹れたてのティードリンク」の提供を始めた。

ゴンチャ(2015年)
ゴンチャが「ハンドシェイクティー」(蓋付きの携帯タイプの容器に材料とお湯を入れ、自分で振って混ぜて作るタイプのミルクティー)を発売した。

滬上阿姨(2013年)
2013年に上海で誕生した「滬上阿姨」は、「赤もち米ミルクティー」で「穀物+ミルクティー」という新スタイルを切り開いた。

茶顔悦色(2013年)
同年、長沙で誕生した「茶顔悦色」は、「新解釈の中国茶」を理念に掲げ、ロゴマーク、商品名、パッケージ、店舗の内装を中国風に徹底し、看板メニューの「幽蘭ラテ」で、並んででも飲みたいという消費者を数え切れないほど生み出した。

奈雪的茶(NAIXUE奈雪の茶)(2015年)
2015年創立の「奈雪的茶」(NAIXUE奈雪の茶)は、新鮮な果物を使ったフルーツティー飲料を全面に打ち出しており、「霸気玉油柑」や「鴨屎香シリーズ」がことのほか有名だ。

喜茶(HEYTEA)(2017年)
2017年創立の「喜茶」(HEYTEA)は、「多肉葡萄」「芝芝莓莓」などの大人気メニューを開発した。

茶百道(2020年)
2020年創立の「茶百道」も、伝統的な香港デザートである楊枝甘露を自社の看板メニューに据えた。

霸王茶姫(2017年)
2017年に雲南省で誕生した「霸王茶姫」は、当時のフルーツティーの熾烈な競争レースを避け、「茶+牛乳」で作る主力製品の開発にこだわった。「伯牙絶弦」、「桂馥蘭香」などの看板メニューと、世界的ブランドにも引けを取らないパッケージデザインを武器に、2023年には中国で最も支持されるニュータイプ茶系飲料ブランドの1つに成長し、新店舗がオープンするたびに客であふれかえるほどになった。消費者からは、「『伯牙绝弦』は本当に美味しい」「茶馬古道の風情あふれる藍染め模様の袋も美しい」との評価を得ている。


1日1杯のお茶を飲む現代の中国人
ニュータイプ茶系飲料は今や、中国のいたるところに進出しており、非常に身近な存在になっている。将来は、「1日1杯の茶」が「1日1杯のコーヒー」と同じようにごく当たり前のことになるかもしれない。ニュータイプ茶系飲料がビジネスとして成功したのは、間違いなく中国人の購買力の向上が根底にある。だが、なぜ「茶」なのだろうか。それはやはり、中国人が伝統的な茶文化を愛しているからだろう。ともかく、中国に遊びに行った際は、ぜひ中国「シン・茶系飲料」の様々な看板メニューを味わってみてほしい。そこには私たちアジア人に共通する味覚の秘密が隠されているかもしれない。





関連する日中2か国語記事は『聴く中国語』2024年9月号に掲載中です。
ぜひチェックしてみてください〜〜

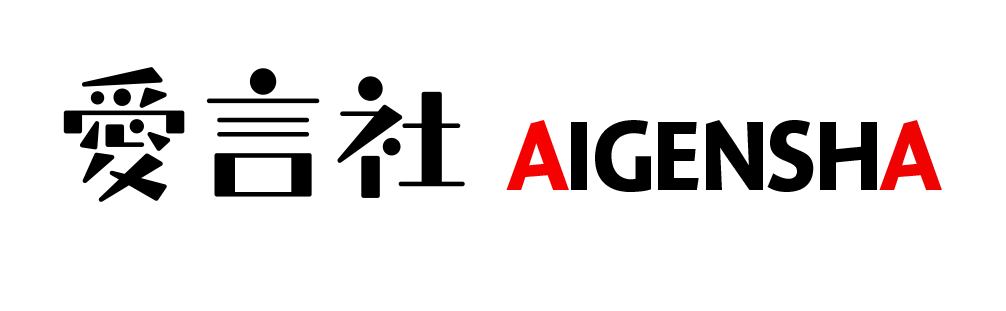



コメント