初めまして。最近まで「全国通訳案内士」(以下、通訳案内士とする)という国家資格に6年かけて挑んだ五弦(名前の由来はコラムの最終回で種明かしします)です。私は2010年代に中国で勤務していた、現在は日本在住の40代日本人女性です。こちらのコラムでは「通訳案內士」に興味を持ってもらい受験生がもっと増加するといいな、という思いを込め「通訳案內士」に関する様々なテーマで書かせていただきます。
約1年にわたってお届けしてきた『通訳案内士への道』。今回は最終回ということで、「これまでの振り返りと次のステップ」をテーマにお送りします。
通訳案内士試験の主な特性
通訳案内士試験について、あらためてその特性を振り返ってみましょう。
・中国語検定やHSKに比べ、通訳案内士試験はまだマイナーな存在ですが、国家資格であり、合格率は例年10%前後と極めて狭き門です。
・受験者数は近年わずかに減少傾向にあるものの、難関試験としての位置づけに変わりはありません。
【一次試験】
・通訳案内士試験は一筋縄ではいきません。特に「地理・歴史・一般常識」は、時に奇問・難問のオンパレード。安易に挑むと“モグラ叩き”状態で何年も受験し続けることになりかねません。
・HSK6級、日本歴史検定2級以上、国内旅行業務取扱管理者などの資格を取得すれば、科目免除が得られます。できれば全てそろえてから本格的に臨むのが理想です。
【二次試験】
・歴史や地理の知識は「知っている」だけでなく、「説明できる」ことが求められます。一次対策中から、説明力を意識した学習が大切です。
・中国語力の底上げも欠かせません。とにかくアウトプットあるのみです。
【試験全体】
長期戦になることを見据え、ロードマップを立てることが重要です。「いつまでに何を終えるか」を可視化しておくことで、モチベーションの維持にもつながります。
通訳案内士試験は、「外国語 × 日本理解 × 実務対応力」が一体となった国家試験です。単なる語学力ではなく、日本の魅力を伝える“表現者”としての資質とプロ意識が問われる点が最大の特徴です。
通訳案内士に求められる5つの特性
1.高度な語学力と文化的表現力
単なる翻訳力にとどまらず、日本文化や歴史・地理を魅力的に伝えるプレゼンテーション力が不可欠です。たとえば、清東陵を案内した中国人ガイド・李さんのように、歴史的背景を深く理解し、いきいきと語る力が求められます。
2.卓越したコミュニケーション能力
ゲストの関心や反応に合わせて柔軟に説明を調整する力、対話を通じて信頼関係を築く力が必要です。観察力と応答力の両方が問われます。
3.幅広い知識と継続的な学習意欲
日本に関する幅広い知識に加え、常にアップデートされる観光事情にも対応できるよう、学び続ける姿勢が求められます。
4.ホスピタリティと対応力
通訳案内士は、単なる“案内人”ではありません。旅行全体を円滑に進行させるため、トラブルや変更にも臨機応変に対応できる力が大切です。
5.エンターテインメント性とプレゼン力
ユーモアやエピソードを交えながら、ゲストを“楽しませる”演出力もまた、良いガイドの条件です。
中国語通訳案内士の仕事のニーズ
・通訳案内士の資格自体が見直されつつあり、インバウンド回復に伴い、今後の需要拡大も期待されています。
・ただし、エージェント経由の仕事依頼はまだ限られており、「対応できる人材が少ないため、あえて案件を設けていない」という矛盾した状況も見られます。
・自ら仕事を獲得する姿勢も大切です。たとえばNさんのように「ドライバーガイド」として独自のスタイルを確立できれば、より柔軟に活動の場を広げられます。
それで、どうする?
多様性が求められる現代において、「日本文化」という固有の世界を理解することは、今まで以上に重要だと感じます。通訳案内士の勉強は、語学力の向上だけでなく、自分の内面を深く見つめ、日本を再発見する旅でもあります。私自身も、通訳案内士という資格を通して、学び続ける人生の良さを再認識しました。もしこのコラムをきっかけに、誰かが興味を持って一歩踏み出してくれたら、それが何よりの喜びです。
ちなみに私は今年、「国内旅行業務取扱管理者」の資格取得を目指しています。合格すれば通訳案内士試験での免除科目がそろい、今後は「一般常識と通訳案内の実務」のみで受験できる見込みです。2次まで通過する可能性が高くなるので、気軽に年1回挑戦するスタンスで、50代までに取れればいいなと構えています。
受験界隈には「9年挑戦しました!」という方もいて、むしろそれが勲章のようになっていたりします(笑)。人生100年時代、焦らず、でも熱意を持って、自分のペースで進んでいければそれで十分だと思っています。しかし、通訳案内士たちの集まりを見ていると、ユニークで癖強そうな人も多く、「早く自分もあの中に加わりたい」という気持ちも出てきます(笑)。
「五弦」に込めた想い

最後に、私のペンネーム「五弦」の由来について少しお話しして、この連載を締めくくりたいと思います。通訳案内士の勉強を始めた当初、私の心に深く残った言葉のひとつが「五弦琵琶」でした。奈良・正倉院に所蔵されているこの楽器は、世界にただ一つ現存する五弦の琵琶です。通常は四弦が主流の中、この五弦琵琶はかつて唐代の中国で作られ日本に伝わりましたが、本国ではすでにその原型が失われています。
この貴重な楽器は、聖武天皇の遺愛品として、東大寺大仏開眼の際に正倉院に納められ、千年以上の時を越えて大切に守られてきました。その存在自体が、日中の文化交流の豊かさと美しさを物語っているように思えたのです。
「たった一つの存在でも、時を超えて意味を持ち続けることがある。」
五弦琵琶には、そんな静かな力を感じます。だからこそ、自分も学びを通じて、何かを伝え、つないでいけたら――そんな想いから「五弦」という名を選びました。
これから受験される方へ。まず、その挑戦する意志だけでも、十分に尊いことだと私は思います。どうか焦らず、自分のペースで歩んでください。もしかしたら、いつかどこかの現場や研修で、読者の誰かとお会いすることがあるかもしれません。そんな小さな夢と妄想を胸に、この連載を終えたいと思います。

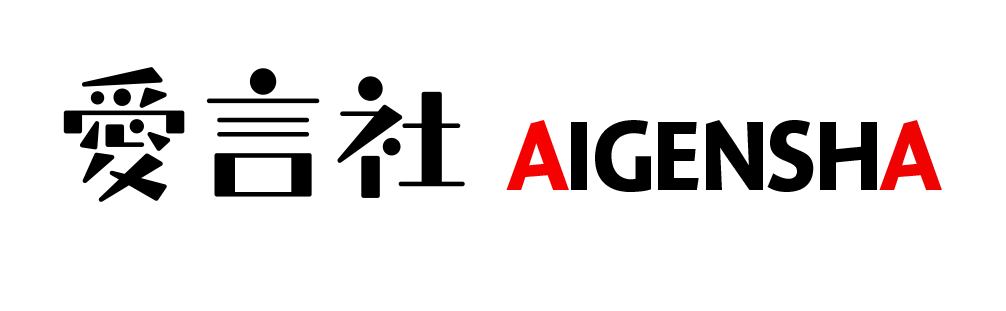



コメント