中国語語学誌『聴く中国語』では日中異文化理解をテーマにしたコラムを連載しています。
今回は日本中国語検定協会理事長の内田慶市先生が執筆されたコラム、うっちーの中国語四方山話−異文化理解の観点から⑧ “恢复疲劳”って「疲労を回復する??」—中国語の動詞と目的語との関係—をご紹介します。
「疲労回復にリポビタン何とか」というコマーシャルがありますが、今回はこの「疲労回復」について考えてみようと思います。
「中国語の基本的語順は「動詞+目的語」ですが、目的語は普通、動作行為の「対象」です。従って、“恢复” という動詞に“健康”という目的語を付けたら「健康を回復させる」となりますね。“恢复职称”ならば、「身分を回復する」という意味です。従って、“恢复疲劳”と言うと「疲労を回復させる」という意味になってしまいますが、「疲労を回復させる」のではたまったものではありません。つまり、本来は“消除疲劳”(疲労を取り除く)という意味のはずです。ただ、“恢复疲劳”は“消除疲劳”と全く同じ意味ではありません。単に「疲労を取り除く」という意味の他に「体力、或いは健康を回復する」という意味を含んでいます。
実は中国語の「動詞+目的語」の関係は、英語のように単純な「矢と的」との関係ではありません。

例えば、“救火”とか“养病”などよく考えると奇妙な構造です。“救火”は「火を救う」ことではありませんし、“养病”も「病気を養う」という意味ではありません。“救火”は“灭火”(火を消す)という意味ですが、“灭火”と“救火”はイコールではありません。「コンロの火を消す」は“救火”とは言いません。すなわち、これらの構造は「動作と原因」の関係を表していると言うことが出来ます。中国語で説明すると、“救火”とは“因为发生了火灾,所以要抢救”であり、“养病”も“因为生病,所以要休养”ということなのです。上の“恢复疲劳”も同様で、“因为疲劳,所以要恢复体力。”ということです。

こうした例は他にもたくさんあります。“后悔没有去”(行かなかったことを後悔する)“难过什么?”(何が心配なの?)“你哭什么?”(何を泣いているの?)“你笑什么?”(あなたは何を笑っているの?)などもみなこの「動作+原因」の関係です。

いずれにしても、中国語の動詞と目的語の関係は複雑です。
これは日本語でも同じなのですが、「トンネルを掘る」(“挖隧道”)とか「小説を書く」(“写小说”)もよく考えるとおかしな構造です。「トンネル」や「小説」はその動作を行った後にできる結果です。「お湯を沸かす」もお湯からでなくて「水」から湧かします。
一応、中国語の動詞目的語関係は大きくは次の6つにまとめることが出来ます。
(a)“坐火车”(汽車に乗る)=場所
(b)“到上海”(上海に着く)=ゴール
(c)“抽烟斗”(キセルで吸う=道具
(d)“下雨”(雨が降る)=主体
(e)“写字”(字を書く)=結果
(f)“洗衣服”(服を洗う)=対象

今回紹介したコラムは『聴く中国語』2024年11月号に掲載しております。

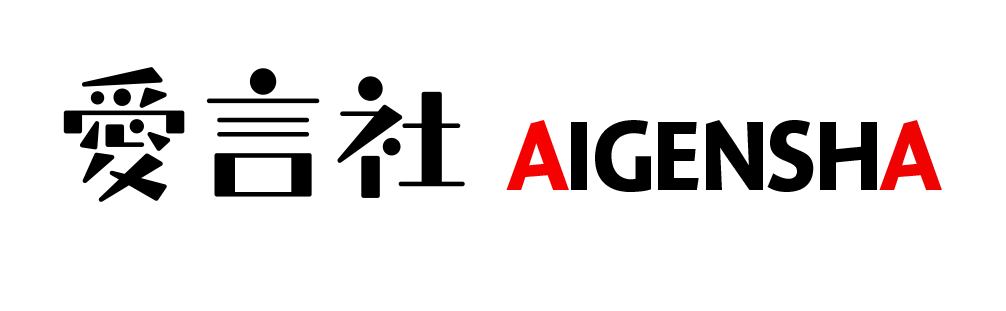



コメント