初めまして。最近まで「全国通訳案内士」(以下、通訳案内士とする)という国家資格に6年かけて挑んだ五弦(名前の由来はコラムの最終回で種明かしします)です。私は2010年代に中国で勤務していた、現在は日本在住の40代日本人女性です。こちらのコラムでは「通訳案內士」に興味を持ってもらい受験生がもっと増加するといいな、という思いを込め「通訳案內士」に関する様々なテーマで書かせていただきます。
こちらの原稿を書いている際に、2次試験の合格者が発表されました。今年の中国語合格者は31名でした。受験された方は本当にお疲れ様でした。合格すると『官報』に氏名が掲載されますので、一生ものの宝になることかと思います。残念だった方も、前回記述したようにかなり「お題ガチャ」もあるかと思いますので、まずはその頑張った努力を自分でねぎらってくださいね。
私は2次試験を一度しか受験していませんので1次試験と比べ述べられることは少なくなりますが、参考にしてくだされば幸いです。これを完璧にやっていれば合格できたかもしれない、という妄想込みで書きます。
ロードマップ
1次合格発表から2次受験までは3ヶ月程しかありません。中国語がバイリンガルレベルの方は1次受験後から詰込みまくったら間に合うかもしれませんが、そうでない限りは1年から半年くらいは対策に時間をかけるべきだと思います。※会話が中~上級くらいの方を想定して書きます。
そして、2次もやはりインプットとアウトプットを意識して対策するのがいいように思います。イメージ的にはインプット3ヶ月、アウトプット3ヶ月くらいでしょうか。こう考えると意外と時間がないです。インプット時期は1次試験と重なりますが、地理や歴史を勉強しながら中国語ならどう言うのかを意識するのもいいかもしれません。できれば1次終わった時点でアウトプットができると理想です。
“いかにできないか”を知る
本当にお試し感覚で、その辺りの日本の事象をなんでもいいのでまずは日本語で2分くらいプレゼンしてみてください。神社でも、盆栽でも、お墓でも目に入ったものなら何でもいいです。私はあと1点あれば2次に進めることになった際に、これを気軽にやってみたんですが、まあできない(笑)どのように説明するか構成がまとまらないし、1分くらいで終わってしまいます。合格する方はどれだけレベルの高いことをやってのけたんだと絶望しました(笑)
日本語でできないことを中国語でやろうとしてももっとハードルが上がると思います。
プレゼンに関しては、最終的には「自分の型」のようなものができればいいと思っています。正直、これだけ生成AIが出回っているこのご時世で「〇〇を2分間で中国語で説明してください」と打てば、優秀な答えがぱっと出てきます。この答えを暗記するのがどれだけナンセンスか分かりますよね。やってはいけない勉強法ですね。
インプット:プレゼンテーション
自分の型を作るにしても、まずは基本を組み立てていく必要があります。崩すことは後からいくらでもできます。
プレゼン導入部分はインプットで乗り越えられます。世の中に過去問が出回っていますので、それを参考に100~500題くらいの問題に対し「○○は△△です」という定義をバッとインプットします。お題が出てきたときもこれを慌てず出すことができれば落ち着くと思います。「門松」を例にとると、定義は以下のようになります。
例:門松 ⇒ 門松は飾り物です。
これが完全にインプットでき、ある程度量がこなせたら、次に5W1Hを意識して構文を作っていきます。
5W1H=「When:いつ」「Where:どこで」「Who:誰が」「What:何を」「Why:なぜ」「How:どのように」
門松 ⇒ 門松は正月に(When)日本の家の門などに(Where)(日本人が=Who)立てる飾り物(What)です。
(Why)門松は、新年に歳神様(としがみさま)を家に迎え入れるための縁起物です。
(How)主に松・竹・梅を使って作られます。松は長寿、竹は成長と強さ、梅は厳冬に咲く生命力の象徴です。
あとは簡単な説明を付け加えてもいいです。
一般論(説明1)⇒ 門松は12月末に飾り、1月7日ごろに片付けるのが一般的です。
ここまでで基本的な説明は完成です。これを慣れるまで練習するのがいいかと思います。ゆっくり考えながらとここまでで1分くらいかかるのではないでしょうか。

説明部分
続きは以下のように話を膨らませていきます。これに関しては覚えている知識を総動員しながらアドリブになるかもしれません。
歴史(説明2)⇒ 歴史をさかのぼると、平安時代から門松を飾る風習がありました。当時は松だけを飾っていましたが、後に竹が加わり、現在の形になったと言われています。
現状(説明3)⇒ 現代では、家の玄関や企業のビルの入り口に飾られることが多く、新年の幸福と繁栄を願う意味があります。伝統文化として受け継がれる門松ですが、最近はコンパクトなものやデザイン性の高いものも登場しています。
以下のように自分のケースを言うことでも面接官の注意を惹きつけられます。
補足(説明4)⇒ うちはマンションのため、飾るところがないので、小さいものをスーパーで買って部屋の中に飾ります。
締め ⇒ お正月に日本に来られた際はぜひ日本の門松を見てみてください!(明るくいかにもガイド風に)
こんな感でしょうか。これを全部話すと2分越えるので、不要部分を削ぎ落としながら話すイメージです。
インプット:日中通訳問題
逐次通訳問題の語彙や文法に関しては、プレゼンテーション対策と平行してやってもいいかと思います。が、こちらもまず、世に出回っている過去問を一通りやってみてください。メモをとってもOKで、日本語が読まれてから30秒以内に開始する必要があり、1分30秒以内に言い終わる必要があったかと思います(※この時間に関しては本番言われたり言われなかったりするかもしれません。また年度によって変わっているかもしれません。)本番さながらでやってみてください。今だとAIを活用して、日本語文章を読んでもらい、自分が訳した中国語を音声で吹き込んで添削してもらうのもいいかもしれません。
おそらくすぐ訳し始めないと1分30秒以内に訳し終わらないことも体感できるかと思います。
私はこの逐次通訳問題の対策で、初めて「リテンション・リプロダクション(リプロ)」という通訳用語に触れました。
リテンション…聞いた話を正確に記憶する
リプロダクション…リテンションした内容を正確に再現する
通訳者が専門的に行うトレーニングですが、通訳とは何かを考える上でこの方法はとても参考になりました。本格的にトレーニングするには時間が限られますが、YouTubeなどでも練習方法が出回っているので参考にされるのがいいかと思います。
しかし正直なところ、中国語がネイティブレベルの方は、日常会話の延長で何も練習しなくとも通訳問題は難なくこなせてしまうような気がします。うらやましい!
メモの取り方の練習
これも通訳者でしたら当たり前にやっていることかと思いますが、言われた文章を一語一句記憶したりメモすることは不可能なので、自分なりの省略記号を決めておくことが重要です。これは後々のアウトプットの時に活かせます。
例えば、第5回で紹介した過去問を例にとってみます。
七五三は、男の子の年齢が3歳と5歳の、女の子の年齢は3歳と7歳のための行事です。11月15日に行われて、健康や成長を祈って、社寺にお参りに行く。現在はその日より1か月前後の期間に参拝する人もいます。
この頃になるときれいな衣装を着た子どもたちの姿が見られます。七五三に欠かせない千歳飴は、いつまでも健康で長生きをしてほしいという意味があります。

ここでは「七五三」がキーワードとなるので、瞬時に◯印に「七」と書くよう設定します。
「11/15」「3」「7」など数字はメモ取り必須です。
あとはこんな感じでしょうか。私はよく英語も併用していました。
・男の子 ⇒ ♂ 女の子 ⇒ ♀
・~のための ⇒「for」
・祈る ⇒「wish」
・1ヶ月前後 ⇒ 「←1m→」(mはmonth=月)
・千歳飴 ⇒ ◯印に「ち」
・意味がある ⇒ 「means」
過去門を解きながら頻出する単語は、省略記号を決めてもいいと思います。
・日本人 ⇒ J
・中国人 ⇒ C
・伝統的 ⇒ Tr
シチュエーションに関しては、こちらも過去問とどういった返答するのがいいか、というのが出回っているので、いったんそれにすべて目を通してください。
参考書
数は少ないですが、2次対策用の参考書があります。手を拡げ過ぎず、これと思うものをインプットの参考にされるといいかと思います。私は4冊ほど購入したのですが、使い込んだのはこの2冊です。
中級・・・中国語で案内する日本
上級・・・中国語でガイドする関東の観光名所10選
とくに後者は内容的にはかなりレベルが高いのですが、巻末にジャンルごとに一言で説明するポイントがまとめられており、導入部分の作成などに大変重宝しました。
次回は「2次対策・アウトプット編」です。
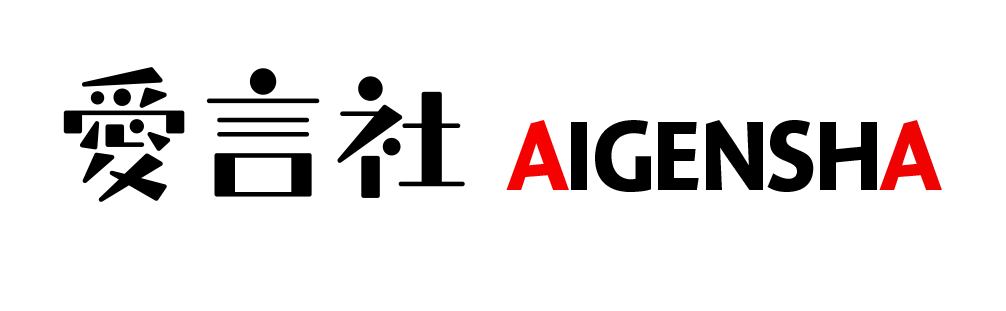



コメント