初めまして。最近まで「全国通訳案内士」(以下、通訳案内士とする)という国家資格に6年かけて挑んだ五弦(名前の由来はコラムの最終回で種明かしします)です。私は2010年代に中国で勤務していた、現在は日本在住の40代日本人女性です。こちらのコラムでは「通訳案內士」に興味を持ってもらい受験生がもっと増加するといいな、という思いを込め「通訳案內士」に関する様々なテーマで書かせていただきます。
インプットができれば、あとはひたすらアウトプットです。
ここではアウトプットのポイントについてお伝えします。
とりあえず中国語の“口”を取り戻す
普段から中国語を話している方は問題ありませんが、私のように中国語を話す環境から数年遠ざかっている場合、中国語の“口”を取り戻す時間が必要です。そのため、2次試験を受ける前年の年末頃から「Super Chinese」というアプリを利用し、課金して遊び感覚で会話練習をしていました。このアプリはAIが発音をチェックしてくれるなど、非常に優れた機能を備えており、通常の中国語学習にもおすすめです。久しぶりに中国語を話すことが楽しくなり、一気に最高レベルまで達成しました。
オンライン中国語レッスンを利用
受験年の春頃から8月までは、オンライン中国語スクールのレッスンをほぼ毎日受講しました。イラストを見て説明する、要約する、瞬間的に通訳するといった、2次試験に直結しそうなレッスンを多種多様にこなしました。もっと会話力を高めたいという焦りを抱えつつ、1次試験終了後には通訳案内士2次試験対策のレッスンへと切り替え、毎日25分間のプレゼンテーションと逐次通訳を1題ずつこなしました。
通訳案内士対策講座を提供しているオンラインスクールは少ないですが、私が年明けから受講したスクールには偶然設けられており、とても助かりました。毎回、講師に過去の試験問題を3題出してもらい、その中から1つを選んでプレゼンテーションを実施。また、逐次通訳の練習では、講師が読み上げた内容をその場で通訳する実践的な訓練を行いました。講師の多くは日本語をある程度理解できたため、中国語でどうしても説明できない時は日本語で伝え、中国語で適切な表現を教えてもらうこともありました。
2次試験の2週間前までには100題を終えました。毎日出題された3題について、うまく表現できなかった部分を確認し、知識がまとまっていない箇所を復習するのに多くの時間を費やしました。この時期はまさに受験生のような生活でした。
ただし、2次試験全体の内容を正しく理解している講師はほぼいないため、シチュエーション問題の対策はオンラインレッスンでは難しかったです。

有資格者に面接官を依頼
そこで協力をお願いしたのが、同じ大学の先輩で通訳案内士資格を持つTさんです。たまたまTさんを知る方と会食した際、その方から「Tさんに面接対策をしてもらった」という話を聞き、紹介してもらうことができました。Tさんは以前の試験形式で合格されており、現在の試験形式での受験経験はありませんでしたが、すぐに試験内容を理解して面接官を引き受けてくださいました。
特にシチュエーション問題では「試験で聞かれそうな内容」を的確に出題してくださり、アドリブ力が試されました。私がうまく対応できない場合でも、Tさんが流暢な中国語で模範解答を示してくださり、大変参考になりました。さすが現役通訳案内士、日本文化にも精通されており、先輩に追いつきたいという気持ちもモチベーション向上につながりました。
通訳案内士スクールでは2次試験対策を行っているところが多いですが、ほとんどが英語向けです。中国語向けには直前対策の講座が1校のみありましたが、料金が高めだったため私は利用しませんでした。しかし、受講した方によると、フィードバックもあり非常に有益だったそうです(その方は合格されていました)。
もし周囲に有資格者がいればラッキーです。ただし、それは稀なことかもしれませんので、知人の中国人に面接官をお願いするのも一案です。私は知り合って間もない中国人にも何度か面接官をお願いしましたが、その際に印象的だったのは「単に知識を披露するだけではなく、相手を楽しませることも大事」という指摘でした。オンライン講座でも「ユーモアが大事」と指導する先生がいました。また、「笑わせることができれば合格」という都市伝説も耳にしましたが、実際はそんな余裕はありません!(必死)。
さらに、実際の中国人に試験官をしてもらうことで「こういう時はこの情報を教えてもらえるとありがたい」といった、受験者目線では気づかないフィードバックを直接もらえたのも良かったです。

独りで練習
オンラインレッスンや対人レッスン以外の“独り対策”としては、ぬいぐるみに向かって話しかける方法を試しました。また、中国語がまったく分からない夫を前に練習することもありました。自宅での練習では動画を撮影し、目線、スピード、間、表情などを確認しました。「もっと抑揚をつけたほうが良いな」といった気づきも多く得られました。また、普段から声を大きめに出すことも意識しました。

その他、身近な日本の事象を見つけるたびに、それについてひたすら声に出して説明する練習も行いました。
日々プレゼン練習を続ける中で、得意な題材と苦手な題材に差があることに気づきました。例えば私の場合は「食」の分野に強く「社会的な事象」が弱かったです。余裕があれば、苦手分野を克服しておくことも重要です。
まとめ
2次試験は、基礎的な会話力をベースに、1次試験で得た知識を活用するものです。対策に時間を割く余裕はあまりないかもしれませんが、シチュエーション問題では、どこでどんな単語を使うことになるかわかりません。普段から語彙のストックを増やすことが大切です。基礎的な会話力は一朝一夕で身につくものではないため、日頃から底上げを意識すること。そして、2次試験対策はひたすら実践練習を重ねることが鍵となります。
また、「ホスピタリティ」も審査の対象となるため、練習の段階から観光客に寄り添う姿勢を持ってトレーニングするのが良いでしょう。
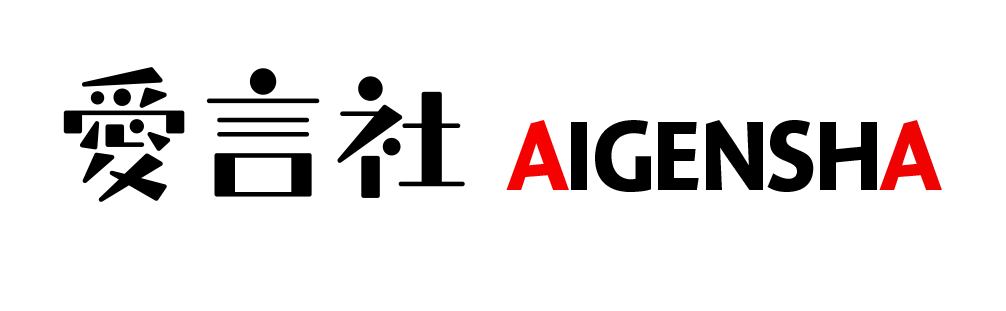



コメント