中国語語学誌『聴く中国語』では日中異文化理解をテーマにしたコラムを連載しています。
今回は日本中国語検定協会理事長の内田慶市先生が執筆されたコラム、うっちーの中国語四方山話−異文化理解の観点から⑫ 中国語の数字の話(2) をご紹介します。
昔、アメリカに住んでいたとき、当時はフィルムカメラを使っていたが、写真屋にフィルムの現像を出しに行くと、店員さんから“Wait five minutes”と言われた。それで、5分経ってから再び写真屋さんに行くと、そんなに早くできないと言われた。「でも、5分待って」と言ったじゃないかと聞くと、店員は変な顔をしていた。それで、初めて、なるほど、この「5分」とは実際の「5分」の意味ではないのだと言うことが分かった。「少し」と言うことだし、しかも、この少しは1時間ぐらいでもその範囲に含まれるのだということも分かった。

“couple” なども同じことであり、“a couple of days”とか“the next couple days”は「2日」ではなくて、「2,3日」「数日」ということである。
ついでに言うと、英語で“see you later”は「また後で」だが、この「後」は1年以上でも使えたりする。
実はこのことは中国語でもよくある現象である。
“过两天再说吧”は「2日経ってからのことにしよう」ではなくて「2,3日経ってから」だし、“我来说两句”は「私から少しお話ししましょう」ということになる。
「3」も同様で、昔,中国の斉の国に管仲という政治家がいた。若い時代には一向に芽が出ず、“吾嘗三戦三走(私はかつて三度戦い、三度走る)”と『史記』(「管鮑之交」=互いによく理解し合った、変わらぬ友情のこと)にも記載されているが、この「三」は実際の「3回」とか言うことではなくて、「何度も戦ったが,その度に敗走した」ということである。つまり、実際の「三」という意味の他に、「幾つも」という意味も含んでいるということである。同じ「管鮑之交」には“吾嘗三仕三見逐於君”というのも出て来るが、この「三」も「私は、かつて多くの君主に使えたが、そのたびに君主にお払い箱にされた」という意味である。
実は「三」が含まれる漢字には、いずれも「幾つも」「多い」という意味が隠されている。

「杉」(木+三)=細い針葉が幾つも集まって出来ている

「衫」(衣+三)=下着の総称だが、「シャツ」、「襦袢」、「胴巻き」等々がみなその仲間である。
ちなみに「森」も「木」が三つから出来ていますが、つまりは沢山の木がある場所というわけである。
もちろん、“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”(三人寄れば文殊の知恵)の「3」は文字通りの意味である。

ところで、中国語の数字には組み合わせで使う場合も多い。
例えば、「3」と「4」の組み合わせには次のようなものがある。
“推三阻四”とは“推脱不止一次”(あれこれと口実を設けて何度も断ること)、“低三下四”は“恭顺的表现不止一个方面”(やたら相手にペコペコして、こびへつらうこと)、“朝三暮四”は“变来变去,反复无常”(考え方や方針が定まらない,常がない)ということで、いずれにしても「三」と「四」の組み合わせは「一度或いは一つの方面だけに止まらない」という意味が含まれる。
「7」と「8」の組み合わせも面白く、多くは「ふぞろい、 雑然とした、乱れた様、ごちゃごちゃ、でこぼこ」といった意味を含んでいる。
例えば、“七嘴八舌”(多くの人があれこれ口を出す)“七手八脚”(大勢の人が寄っていたかって何かをする)“七零八落”(散り散りばらばら)“七上八下”(心が乱れるさま)“七拼八凑”(方々から寄せ集める)“七颠八倒”(話などがひどく混乱しているさま)などがある。なお、日本語でも「七颠八倒(或いは七転八倒)」と言うが、中国語の使い方とは違っているようである。

この他にも“九死一生”“九牛一毛”(多数のうちのごく少数)“千钧一发”(危機一髪)“百闻不如一见”など、数字の対比から派生して使われる成語も多いし、“不管三七二十一”(九九の3×7=21は公理であるところから「是非の理由を問わず」「委細構わず」)のように九九から生まれた成語もある。
なお、“三言两语”(二言三言)は“两语三言”とか“两言三语”とは言えず、“五花八门”(多種多様)は古代の五行陣とか八門陣という陣形から来ているが、これも“六花九门” とかは言えないが、それぞれ何故そうなのかは説明できず、習慣と言うしかないものも多い。
いずれにしても、数字もなかなか奥が深いものである。

今回紹介したコラムは『聴く中国語』2025年3月号に掲載しております。

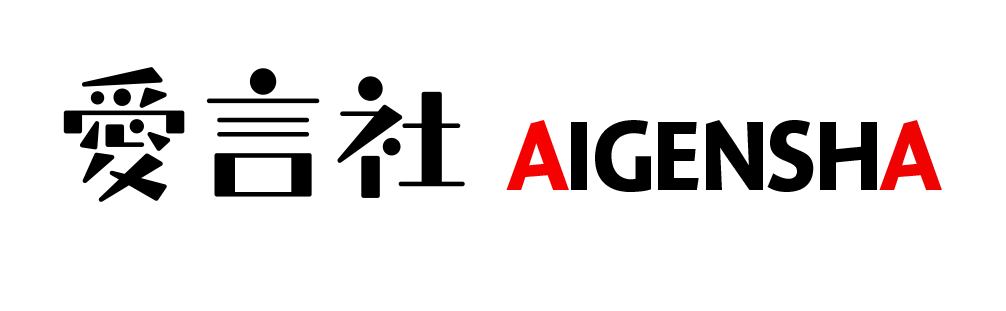



コメント