初めまして。最近まで「全国通訳案内士」(以下、通訳案内士とする)という国家資格に6年かけて挑んだ五弦(名前の由来はコラムの最終回で種明かしします)です。私は2010年代に中国で勤務していた、現在は日本在住の40代日本人女性です。こちらのコラムでは「通訳案內士」に興味を持ってもらい受験生がもっと増加するといいな、という思いを込め「通訳案內士」に関する様々なテーマで書かせていただきます。
さて、ここまで通訳案内士試験の2次試験について見てきましたが、合格する人と不合格になる人の違いは何でしょうか。
私自身、多くの受験者を直接見てきたわけではありませんが、周囲の人やSNSなどで交流した受験者たちの言動から、いくつか推測できることを書きます。
不合格ケース
私の知人である受験者Bさんは、中国駐在歴約8年、大学では中国文学を専攻し、中国語も堪能な同級生です。周囲からも「合格するだろう」と期待されていましたが、初めての2次試験で不合格となりました。私が面接の様子を聞いた限りでは、特に落ちる要素がなさそうに思えたのですが、ご本人の分析によると、次のような点が原因だったそうです。
シチュエーション問題で「祇園祭りが台風で中止になった」という設定が出題され、面接官が「どうしても京都の祇園祭りを見たいんだ!」と駄々をこねる場面がありました。Bさんは、雨でも行ける観光スポットを考え、「刀剣を展示している施設」を代替案として提案しました。しかし、後になって「祇園祭りが展示されている施設を案内すればよかったのかもしれない」と反省していました。
シチュエーション問題では、相手とのやり取りが重要になります。複数の選択肢を提示し、「どれがよろしいですか?」と相手の好みを伺うやり取りがあれば、より良い対応だったのかもしれません。
合格ケース
受験者Cさんは、中国駐在歴8年。毎日コツコツと自主トレーニングを積み重ねていました。1日長時間、地道にトレーニングを続け、それをSNSで投稿することで、他の受験生の共感を呼んでいました。
試験では、プレゼンのお題も過去に練習したものが出題され、シチュエーション問題にもスムーズに対応できたそうです。全体的に自信を持って受け答えをし、試験官との対話も円滑に進んでいました。日々の積み重ねが功を奏した結果と言えるでしょう。

面白エピソード
2次試験に合格した方の中には、予想外の質問やユニークな対応で試験官の印象に残った人もいました。以下に、いくつか興味深いエピソードを紹介します。(中国語以外の言語の受験者も含まれています。)
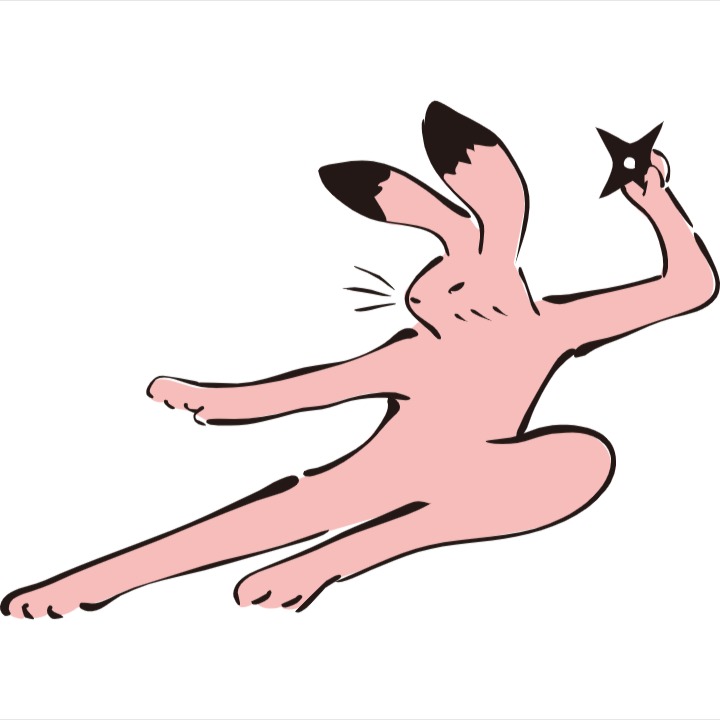
・受験者Dさん:「もしあなたが忍者の末裔だったら、どのような忍術を披露しますか?」という予想外の質問を受けました。一瞬戸惑いましたが、「私は現代の忍術、すなわち卓越したコミュニケーション能力とホスピタリティでお客様をもてなします」と答え、試験官を感心させました。
・受験者Eさん:日本の伝統芸能に関する質問に対し、得意の歌舞伎の物まねを披露し、試験官を笑わせました。そのユーモアと堂々とした態度が評価され、合格につながったそうです。
・受験者Fさん:日本の伝統工芸について説明している際、「実際にその工芸品を使ったことはありますか?」と質問されました。彼はとっさに「はい、自宅で毎日愛用しています!」と答え、その工芸品の魅力を熱く語りました。試験官も興味津々で質問を重ね、まるで工芸品紹介のようになり、試験が盛り上がったそうです。
・受験者Gさん:観光ルートの説明中、「もしあなたが観光客だったら、このルートのどこに一番興味を持ちますか?」と質問されました。彼は「私なら〇〇ですね!なぜなら…」と、まるで友人に観光案内をするかのように熱心に語り、試験官を惹きつけました。
また、プレゼンの冒頭で「私は僧侶をしていますが…」と切り出し、面接官を驚かせた方もいました。直接プレゼンのお題とは関係なかったものの、自分のよく知る世界から話を展開し、興味を引くことに成功したようです。

まとめ
2次試験は、単に知識を問うだけでなく、個性や人間性も重視されます。「おもてなし」の心で相手に寄り添い、対話を大切にすることが合否の決め手となるように感じました。試験対策をする際には、知識の詰め込みだけでなく、対話力や臨機応変な対応力を養うことも重要だといえるでしょう。
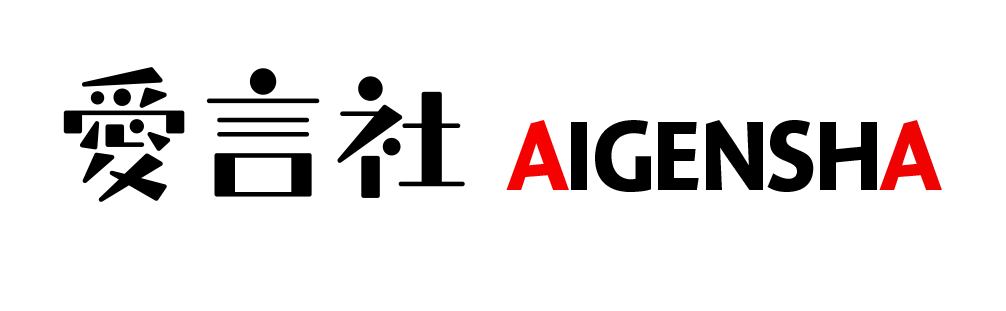



コメント