中国語語学誌『聴く中国語』では日中異文化理解をテーマにしたコラムを連載しています。
今回は日本中国語検定協会理事長の内田慶市先生が執筆されたコラム、うっちーの中国語四方山話−異文化理解の観点から④−具象性を好む中国語をご紹介します。
「具象性」と言うと分かりにくければ、「具体的」と言ってもいいでしょうが、
中国語の特徴の一つにこの「具象性」「具体性」ということが挙げられます。
これは恐らく象形文字を起源とする「漢字の思想」が言語にも反映したものと言うことも出来ます。
例えば、中国語で「(ものを)持つ」という動詞には、“拿”“提”“捧”“端”“托”など様々なものがありますが、それらはそれぞれ具体的な持ち方を示しています。
“端”も“托”も「ものを水平に持つ」ことを言いますが、“端”はスープの入った大きな碗を運ぶ時のように「両手で」持ちますが、“托”は「片手で」持ちます。京都ではよく街の辻に「托鉢僧」が立って布施を受ける姿を見かけますが、その「托鉢」とは「鉢(小さなお椀)を片方の手のひらに載せる」ということです。

「お茶を入れる」には“沏茶”と“倒茶”の二つの言い方がありますが、それもお茶の入れ方の違いです。“沏茶”は湯呑みにお茶の葉を入れてそこに熱いお湯を「チーッと」注ぐ入れ方ですが、“倒茶”は急須でお茶を入れる時に使います。急須を「傾けて(=倒)」茶碗にお茶を入れるわけです。
中国料理では材料の「切り方」の違いが料理名に反映されます。たとえば“青椒肉丝”の“丝”は「細く切る」ということで、“宫保鸡丁”の“丁”は「角切り、サイコロ目切り」ということです。
実は中国語の具象性を示す最も典型的なものは「量詞」の存在です。
ご存知のように中国語ではモノを数えたり、指し示したりする時、必ず名詞の前に「量詞」が置かれます。日本語でもこの現象はあるのですが、しかし、日本語だと指示代名詞の後ろには量詞は用いられません。例えば「1冊の本」と助数詞「冊」を使いますが、「この本」という場合には「この冊の本」とは言いません。しかし、中国語の場合、“一本书”“这本书”という具合にどちらも必ず量詞が使われるのです。
また、名詞によってどの量詞を使うかは決まっており、同じ形状、同じ形態のものには同じ量詞が使われます。従って、名詞の前に長い修飾語が付いた場合でも“一条”と先に量詞があれば後ろに来る名詞がどのようなものか具体的な姿を容易に想像できるのです。

ところで、「具象性」の反対は「抽象性」ですが、中国語はこの「抽象」の弱いところがあります。「望遠鏡」を今は“望远镜”といいますが、「遠くを望む鏡」では中国人にとってはあまり納得いくものではなかったようです。「遠く」と言っても「どれくらい遠く?」ということになるわけです。それで、中国語では初めは“望远镜”ではなくて“千里镜”と言ったのです。「ああ、千里の遠くまで見れる」ということで納得です。“万里长城”も同様でしょう。「一万里」という具体的な長さで「限りなく遠い」ことを表現したのです。
今はどうか分かりませんが、昔は動物園の入場キップや寝台車の料金は120cm未満は無料、150cmは大人料金というように、年齢ではなくて身長で決められていました。年齢は偽ることができますが、背の高さは偽ることができませんから。

ただ、「抽象」に弱いと言っても、社会の発展に伴い、「抽象語彙」も必要になってきます。そこで、それは日本語から拝借するということになったわけですが、この辺りのことについてはまたそのうちお話ししましょう。

今回紹介したコラムは『聴く中国語』2024年7月号に掲載しております。

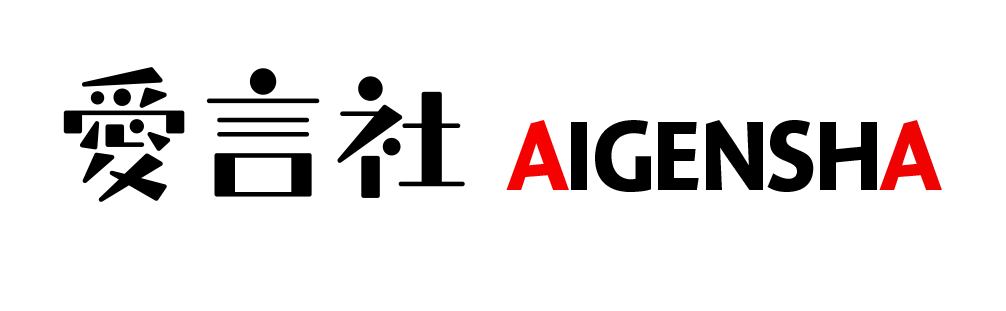



コメント