中国語語学誌『聴く中国語』では中国語学習にまつわるお話をご紹介しています。
今回は日中通訳・翻訳者、中国語講師である七海和子先生が執筆された、「ふるさとの 訛なつかし 停車場の…」というテーマのコラムをご紹介します。
執筆者:七海和子先生
日中通訳・翻訳者。中国語講師。自動車・物流・エネルギー・通信・IT・ゲーム関連・医療・文化交流などの通訳多数。1990年から1992年に北京師範大学に留学。中国で業務経験あり。2015年より大手通訳学校の講師を担当。

皆さん、こんにちは。七海和子です。
「ふるさとの 訛なつかし停車場の 人ごみの中に そを聴きにゆく」
石川啄木の望郷の思いを詠んだ代表作です。岩手県出身の石川啄木は懐かしい故郷の訛りである東北弁を求め、駅の人ごみのなかに「そ」(「それ」のこと)を聞きに行ったのですね。郷愁を感じます。
が!外国人の私たちが中国語の訛りを聞くと、郷愁を感じるどころではなく、「うわー!どうしよう!」と緊張してしまう方が多いのではないでしょうか。
私も同じです。中国人のお客様が話す中国語は、教材で聞くような標準な発音ばかりではありません。いえ、むしろそんなことはほぼありません。声だって、朗々としたよく響く声ばかりではなく、もごもご話される方もいれば、小さい声の方、弾丸トークの方もいらっしゃいます。訛りや声や話し方は千差万別。正確に聴き取れないと通訳できないので、とても緊張しますし、場合によっては慣れるまでちょっと時間を要することもあります。
皆さんが実際に中国の人と交流する場合も同様ではないでしょうか。ということで、今回のテーマは、「訛りも含めてリアルな話し方に慣れる」です。
そこで私がおすすめするのは料理動画です。なぜ料理動画がおすすめかと言うと、ひとつは中国ならでは食材や調理方法を見ることができて、食文化に触れることができるから。そして、1本の動画が短いものなら3分以内、長いものでも5分から8分程度で、気軽に見ることができるからです。動画は字幕もついているので、意味を確認しながら視聴できるのもよいところですね。但し、この字幕、たまに間違っているので、これを鵜呑みにしないほうがよいでしょう。あくまでも全体の意味の把握のために、参考程度にしておきましょう。
私が時々覗いている動画を挙げておきますね。特に書いていなくても、料理はどれもおいしそうです!
马少勤…女性。作っている料理はいわゆる“家常菜”で私たちでも作れそう。鼻にかかった 声が特徴的で若干訛りがあるが、聴き取りやすい。

海娟美食…女性。若干訛りがあるが聴き取りやすい。中国人にしては話すスピードが遅め。そのため、料理中の動作とその際の表現を確認しやすく発見が多い。日本でも入手しやすい材料で作る料理が多く、チャレンジしてみたくなる。

小董美食大全…男性。発音がきれいで声が高めなので聴き取りやすい。中国の“饭馆”で食べるような料理が多く、垂涎もの。中華包丁さばきが見事。

留意美食…男性。スピードは普通。巻舌音が弱いが声が通るので、全体としては聴き取りやすい。

张大神美食…教材ほどではないが、発音がきれい。表現のしかたに参考となるものが多い。

食光白粥…何名かの“UP主”が料理を紹介。家庭料理からちょっと本格的な料理まで様々な料理を見ることができる。訛り率は高く、かなりきつい人もいるので上級者向け。

もちろん、YouTubeをはじめとするプラットフォームには、元記者によるインタビュー動画や時事問題に関する解説動画などがあり、見ごたえもあるし、リアルな中国語を聴くことができます。が、これらは30分程度と長く、内容も予備知識がないと理解をすることが難しいものが多いので、まずは、短くて手軽に楽しめるものから始めるのがよいと思います。
ここでひとつお伝えしたいのは、まずは自分の発音が固まってからこれらの動画を視聴するほうがよい、ということです。目安としては、ある程度まとまった文章(150~200字程度)をピンインなしで読め、巻舌音、子音「f」や「h」の違いなど、中国語の発音・発声を理解できていること。これらの基本を把握してから、訛りに触れることをおすすめします。そうしないと、訛りに影響されてしまって自分の発音が不安定になる恐れがあるからです。
日本語にも各地いろいろな訛りがあって、それぞれに個性的で魅力的ですよね。何より聴いていて楽しい!中国語も同じです。それに「訛りやいろいろな人の声(話し方)に慣れる」と、ヒアリング能力が飛躍的に向上しますよ。その上で折に触れ教材の「標準的な中国語」を聴いてご自身の発音をブラッシュアップしていってください。
ところで、冒頭に紹介した石川啄木の歌ですが、この歌碑がJR上野駅15番線ホームの入り口付近にあるのです。皆さん、上野駅に行くことがあったら是非見てみてください。
今回紹介した七海先生のコラムは『聴く中国語』2025年6月号に掲載しております。

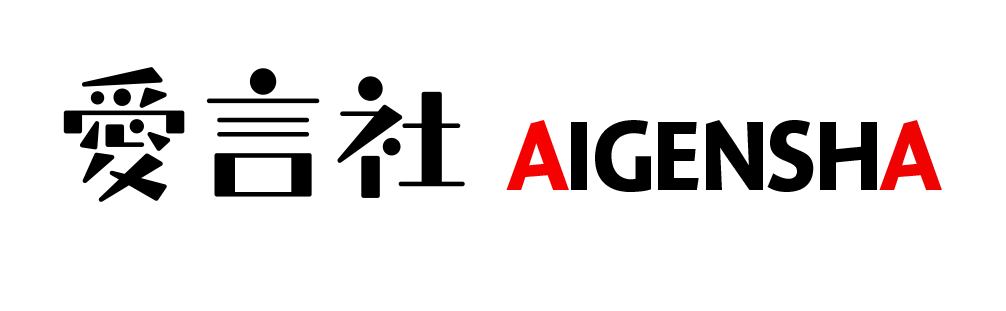



コメント