大家好!年が明け、2025年の干支は「巳(み)」ですね。「巳」という字を見ていると、筆者は学生たちが書いた簡体字の間違いを思い出します。例えば、“已经yǐjīng(すでに)”の“已yǐ”が“巳sì”となり、“巳经”と書いた間違いや、“已yǐ”が“己jǐ”となり、“己经”と書いた間違いなどをよく見かけます。こうした間違いを見て、あらためて漢字の繊細さに気付かされます。“已yǐ”と“巳sì”と “己jǐ”、漢字を全く知らない人からすれば、きっと同じ字に見えるのでしょう。筆者もつい最近、ミッキーとミニーは違うキャラクターであることを知ったのです。学生に「どうやって区別しているの?」と聞いたところ、「まつげが違うんです」と教わり、舌を巻きました。細かい違い、ちょっとした区別…漢字だけでなく、私たちの世界はこうした繊細さで成り立っているような気がします。それを見落とさずに、一つずつ丁寧に拾い上げることが、言語を習得する上でもすごく大事だと思います。

大雑把ではありますが、色んな言語をかじると、気になることがたくさん出てきます。今月は、日本語の「理想」と中国語の“理想”についてです。両者の違いに気づいたきっかけは、韓国語を勉強しているときでした。
韓国語のテキストで、이상을 쫓다(理想を追う)という表現に出会いました。이상は日本語の「理想」と同じ語であり、쫓다は「追う」ですが、テキストには韓国語の이상을 쫓다、すなわち「理想を追う」は、「長い下積み時代を送っているミュージシャン、お笑い芸人などによく使います」と書かれています。つまり、韓国語で「理想を追う」と言えば、「若い人が芸能界での成功をつかむために奮闘する」ことを表すことが多く、日本語の「理想を追う」に比べると、だいぶ意味が限定的だと思いました。
そこで、日本語の「理想を追う」「理想を追求する」をネットで検索してみたところ、どうやら日本語の場合は、「理想」の具体的な中身がわからない例が多いようです。例えば、「理想を追いすぎる傾向にあり……」、「空想的で理想を追う性格を表しています」など。こうした例における日本語の「理想を追う」は、目の前の現実に対して、「より上を目指す」というような意味で用いられていますね。
「이상을 쫓다(理想を追う)」と聞いて、韓国の方は「ああ、いつか努力が報われ、成功するといいね」と思うのかもしれません。一方、日本の方は「あの人は理想を追っているんだ」を聞いて、何を想像するのでしょう。何となく、「ああ、あまり目の前の現実と向き合おうとしない人だな」というふうにとらえる人が多いもいる気がします。同じ漢字や語彙でも、意味が異なるという現象は、日中だけでなく、日韓の間にも見られるのではないでしょうか。

「理想」の話に戻りましょう。日本語では、「芸能界での成功をつかむために奮闘する」ことは、「理想を追う」よりも「夢を追う」で表現したほうがしっくりくると思います。だとすれば、韓国語の이상(理想)はむしろ「夢」の意味に近いです。
中国語の“理想”も「理想」というより、「夢」「志」「抱負」といった意味に近い気がします。例えば、よく聞く言い回しの “人要有远大的理想(人間は大きな志をもつべき)”、“你将来的理想是什么(将来の夢は何ですか)”、“他是一个有理想的人(彼は志がある人/夢をもつ人だ)”というように使われます。また、白水社の『中国語辞典』では“实现当医生的理想”という例文があって、その訳は「医者になる理想を実現する」でしたが、おそらく「医者になる夢を実現する」のほうが日本語として自然でしょう。
ついでに、中国語では、“梦”は睡眠時の夢のことのほかに、「実現不可能な願望」を意味することが多いです。例えば、“你别做梦了,他是不可能喜欢上你的!(諦めな!彼が君に惚れるはずなんてない)”とか。

最後に、中国語の“理想”の形容詞の用法についても触れておきます。日本語からはあまり想像がつかない用法なので、ぜひチェックしておきましょう。形容詞の“理想”は「理想的だ」と訳されていますが、用例を見ると、もっぱら「試験の成績、結果、または条件や環境などが望ましい・望ましくない」場合に用いられています。例えば、“成绩不是很理想”は「成績が理想的とはいえない→成績があまりよくない」という意味で、“考试考得不太理想”は「試験で思うように点数を取れなかった」という意味です。ほかにも、 “效果不很理想(効果があまり出ていない)”、“居住环境不是很理想(居住環境があまりよくない)”、“比赛的票房不是很理想(試合の興行収入があまりよくない)”、“观测条件不很理想(観測条件があまりよくない)”などがあります。これらの例では、“理想”がほとんど“不太理想”や“不是很理想”などの否定形で現れているのも面白いですね。みなさんも何か、期待した通りの結果や効果が得られなかったときに、“○○不太理想”というふうに表現してみてください。表現力アップ間違いなし!
では、また次回お会いしましょう。

今回紹介した先生のコラムは『聴く中国語』2025年4月号に掲載しております。

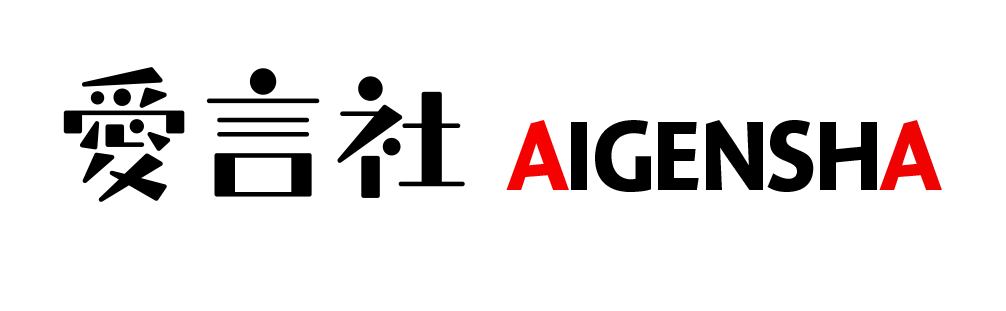



コメント