中国語語学誌『聴く中国語』では中国語学習にまつわるお話をご紹介しています。
今回は日中通訳・翻訳者、中国語講師である七海和子先生が執筆された、「サバイバル中国語!」というテーマのコラムをご紹介します。
執筆者:七海和子先生
日中通訳・翻訳者。中国語講師。自動車・物流・エネルギー・通信・IT・ゲーム関連・医療・文化交流などの通訳多数。1990年から1992年に北京師範大学に留学。中国で業務経験あり。2015年より大手通訳学校の講師を担当。

皆さん、こんにちは。七海和子です。
4月になりました!4月は始まりの季節。新生活がスタートしたり、新たなことに挑戦する方も多いのではないでしょうか。皆さんが希望に満ち溢れたスタートを切れますように。
サバイバル中国語
さて、今回のテーマは「サバイバル中国語」です。これだけではちょっと何を言っているのかわかりませんよね。「サバイバル」なんて言ってしまうと大げさですが、要するに「自分の知っている単語、文法を使ってなんとか自分の言いたいことを伝えよう」、ということなんです。
授業でフリートークをすると、何と表現したらよいのかわからない、その単語を知らないもしくは単語をど忘れしたときに、しばしば「〇〇(日本語)ってなんて言うんですか?」と質問されます。その質問をしたい気持ち、とてもよくわかります!でも、これを日本語の会話に置き換えて考えてみましょう。例えば、「キウイ」という単語を度忘れしてしまったとき、あなたならどうしますか?こんなふうに言うのでは?「えーっとね、果物でね、見かけは茶色っぽくてケバケバしてるの。で、果肉は緑色で、あ、黄色いのもあるけど、甘酸っぱい味なのよ。」このように説明すれば、相手は「キウイ?」と分かってくれるはず。
これを中国語で言ってみましょう。“是一种水果。看起来是棕色的,表面上有细细的毛毛,里边是绿色的,也有黄色的。味道是酸甜的。”こんなふうに言えば、相手はきっと“猕猴桃(míhóutáo)?”と答えてくれるはず。ほら、“猕猴桃”という単語を知らなくても、相手から答えを引き出すことができました!これこそがコミュニケーション!
茶色は“棕色”ですが、知らなければ“咖啡色”なんて言ってもいいし、それも難しければ、近くにある茶色のものを指さして、“这种颜色”と言ってもいいですよね。キウイの上のケバケバは“绒毛(róngmáo)”という単語のほうが雰囲気は出るのでしょうが、そんなの知らなくても“毛毛”で十分です。果肉は“果肉”という単語がありますが、上記のように“里边”や“里面”を使えば十分にわかってもらえます。 “猕猴桃”はたったの一言ですが、単語を知らないときやど忘れしたときは、説明しなければならないので、もっとずっと多く話すことになります。話すためには自分の持っている知識を総動員しなければなりません。こんなふうにして「その単語(表現)を知らなくても、すぐに別の言い方を探す」ことに意識を向けると、知っている単語や構文だけでも多くのことが伝えられるようになり、自分の中国語が「使える中国語」になっていきます。
「正しく言わなくちゃ!」という意識も大切だと思います。が、もっと大切なのは、最初は正確でなくても、自然な表現でなくても、今自分が持っている単語や文法でとにかく言いたいことを伝える、この意識です。言葉は道具ですから、自分の意思が伝えられれば、相手に理解してもらえれば、それでよいのです。
知っている単語で勇気を出して言ってみる!
でも、それだけでは次のステップに行けないので、後で、さらによい表現があるか調べてみると効果が上がります。例えば、先ほどのキウイの話で言えば、「キウイの形って、そういえば楕円形だけど、それはなんて言うんだろう」とか、「食感は柔らかくてジューシーだけど、これは?」のように、ここから展開して、いろいろ調べていけば、もっと詳しい説明ができるようになります。例えば、こんなのはどうでしょう。“有一种水果,外形是椭圆形(tuǒyuánxíng)的;表皮是棕色的,有细细的短绒毛;果肉是绿色或黄色的,有一些小的、黑色的籽(zǐ);口感柔软(róuruǎn),酸甜多汁(duōzhī)。” すでにキウイについては、不完全ながらも自力で説明できています。ここに、さらに調べた新しい単語や表現を加えれば、これらはただ「知っている」「覚えた」レベルではなく、「使える」レベルで身につきます。
単語がわからなくても、自分の言いたいことを表現することは十分に可能です。あとは中国語を口に出す勇気があれば、いつでもどこでも中国語を使って意思疎通が図れます。これがサバイバル中国語です!
中国語を話すこと、会話をすることに「ちょっとハードルが高いなぁ…」と気おくれしてしまう人もいるかもしれません。でも、もっと気軽に考えてくださいね!皆さんがもっと楽しく気楽に中国語を口にすることができますように!
今回紹介した七海先生のコラムは『聴く中国語』2025年4月号に掲載しております。

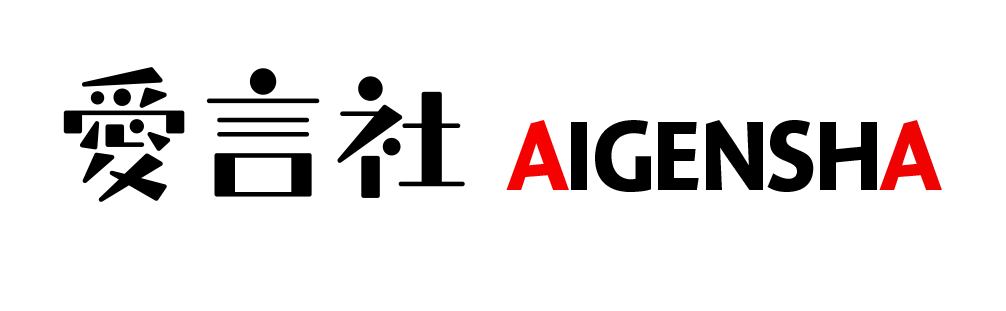



コメント