中国語語学誌『聴く中国語』では日中異文化理解をテーマにしたコラムを連載しています。
今回は日本中国語検定協会理事長の内田慶市先生が執筆されたコラム、うっちーの中国語四方山話−異文化理解の観点から⑮ ウサギとカメ をご紹介します。
「もしもしカメよカメさんよ、世界のうちでお前ほど…」と童謡にも歌われる「ウサギとカメ」はイソップのお話です。


イソップが日本に最初に伝わったのは16世紀末でした。イエズス会の宣教師によって長崎の天草で日本語に訳され出版されました。ただし、全編ローマ字です。中国でもイソップは同じ頃、イエズス会の宣教師であるルッジェリーやマテオ・リッチによって中国語に訳されました。

中国語訳イソップの中で最も有名なのはイギリス人外交官ロバート・トームによって訳された『意拾喩言』というものです。トームのイソップ翻訳の大きな特徴は、話の出だしや、場所、登場人物、教訓を中国風に変えてしまったことです。まさに、「中国人の衣裳を身にまとったイソップ」というわけです。


たとえば、「牝猫とアフロディーテ」というお話では、登場する「アフロディーテ」つまり月の神「ヴィーナス」を中国の伝説に登場する「嫦娥」に変えてしまいました。「ヘラキュレス」は「阿弥陀仏」という具合です。
では、「ウサギとカメ」はどうでしょう。
禹疏九河之時,凡鳥獸魚鱉紛紛逃匿,適兔與龜同行,其兔常罵龜曰,吾見行之迤邐慢頓者,莫如汝也,何不如我之爽快麻利,豈不便捷乎。……

ちょっと古い文体で書かれていますから、難しいかも知れませんが、訳しますと、「昔、大禹(夏の王朝を作った人で、黄河の治水をしたことで有名です)が九河(黄河のこと)の治水を行った時、全ての鳥や獣、魚やすっぽん達がことごとく逃げ出した。その時、ちょうど,ウサギとカメが一緒になったが、ウサギはいつもカメを罵って言うには、お前ほど歩きののろまな奴はいないぞ。どうして、私みたいに速く歩けないんだ?…」ということになります。最後の教訓は「驕兵必敗(おごれる兵は必ず負ける=おごれる平家久しからず)という中国の故事で結ばれています。
話はそういうことですが、今回、問題にしたいのは、その話の「タイトル」です。日本語では「ウサギとカメ」ですし、英語でも「The hare and the tortoise」となっています。ところが、このトームの『意拾喩言』のタイトルは“龟兔”なんですね。今の中国語訳イソップでは“龟兔”の後ろに「かけっこ」を付けて“龟兔赛跑”と言うのが普通です。すでにお気づきのように、日本語や英語のタイトルと中国語では語順が「逆」なんですね。
実は、特に日本語と中国語ではこうした「逆」の例が少なくありません。例えば、最近は「白黒テレビ」はほとんどありませんが、これを中国語で言うと“黑白电视”となります。物の売り買いは日本語では「売買」ですが、中国語だと“买卖”です。
では、どうしてこういう違いがあるのか?それについては、次号で考えてみることにします。


今回紹介したコラムは『聴く中国語』2025年6月号に掲載しております。

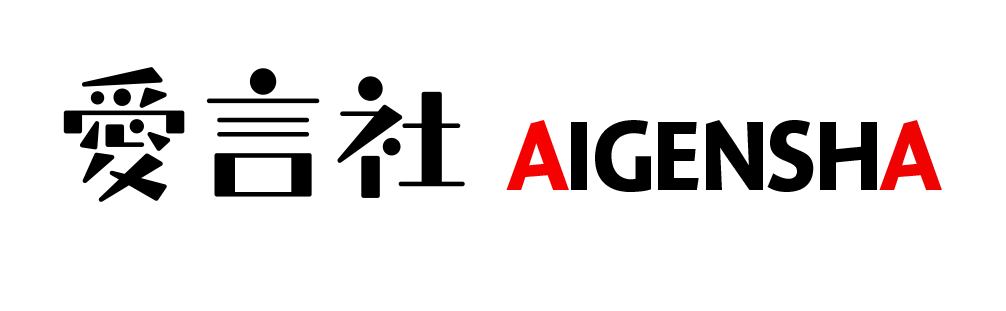



コメント