中国語語学誌『聴く中国語』は毎月、日本で活躍している中国の有名人や日中友好に貢献している日本人にインタビューをしています。
今回は著名華人の佐々木芳邦さんにインタビューしました。文化大革命の反逆者から野村證券ビジネスマンとして活躍するまでの、まるで小説のような激動の20年間。その数奇な経験について伺ってみましょう!
――佐々木さん、こんにちは。読者の皆さんにご挨拶いただけますでしょうか。
こんにちは。佐々木芳邦と申します。もとの名前は尤芳邦と言います。父は台湾人で、1994年に日本国籍を取得し、母の姓に変わりました。
――いつ中国・天津に行き、どこで学校に通われたのですか?当時の中国はどのように目に映りましたか?
1953年、私の父は日本華僑帰国運動の発起人の一人でした。私は3歳の時に両親と共に天津にやって来て、天津で小学校と中学校に通いました。天津に来た時は朝鮮戦争後期だったため、街を歩くと聞こえるのは「威風堂々と鴨緑江を渡る…」というラジオの歌声でした。当時私はまだ3歳でしたので、特に印象は残っていません。
7歳の時、天津浜江道小学校に入学しました。中学校は天津十八中学校(現在はもとの校名に戻り、匯文中学校)です。
私の人生において影響が大きかったのは中学校卒業を控えた頃のことでした。1966年6月1日、人民日報が「旧地主や旧資本家、学界の権威などを一掃する」という社説を発表し、私はこの社説を見て衝撃を受けるとともに、毛主席の革命路線を守らなければならないという一種の使命感を持ちました。

元々、私は毛沢東の信奉者でした。何人かの同級生と相談し、大字報を書いて天津市共産党委員会を批判しました。(天津市共産党委員会が各学校に通知した意見は、人民日報の社説に反対していたため。)今思い返すと、子どもが党に反することをするなんて、余程度胸があったのでしょう。ちょうど「生まれたばかりの子ウシはトラをも恐れない」という中国語の言葉の通りですね。
間もなくして、天津市は天津十八中学校に私を「鎮圧」しに専門のチームを派遣しました。しかし、私は毛主席の革命路線を守ることは間違っていないと思っていたため、彼らと討論しました。
討論会が終わると、作業班は全校生徒を動員して、尤芳邦を批判するための大字報を書かせました。教室の外の壁には「反革命分子尤芳邦を打倒せよ」という標語が書かれ、名前を逆さにして「×」を付けられました。映画でよく見られるシーンと同じです。
それから間もなく、たしか8月5日だったかと思いますが、毛沢東が「司令部を砲撃せよ」という、劉少奇を直接批判する大字報を書きました。その瞬間、私は「反革命」から「造反派の英雄」になったのです。文革も勢い盛んな全国的な群衆運動になりました。
当時、私はある中学校の教員と知り合いました。その方は新聞を作りたいと言い、私はその方と一緒に新聞社を作り、新聞を出版しました。当時天津市では少し有名でした。

その後、「上山下郷」運動が始まりました。当時、私は天津十八中学校の革命委員会の委員でした。毛沢東の革命が成功したのは、「農村から都市を包囲する」戦略を採ったからです。しかし、私は農村のことをよく知らず、革命を引き継ぐ資格はなかったため、農村に行かなければなりませんと考えていました。派出所へ行き自分の戸籍を取り消し、紙を持って校長のもとを訪ね、農村へ行きたいと言いました。校長は感動し、最終的に私に四つの中学校の400名の知識青年を連れて農村に行くことにさせたのです。
(出発する時)天津駅で興味深い場面がありました。(とても忘れがたいものでした)。汽車が出発の音を発し、ガタンと動き出すと、大きな音が轟いたのです。汽車の中にいる人も外にいる人も、出発する人も見送りに来た人も皆大声で泣いていました。(泣いていなかったのは私一人だけだと気づきました。)私の脳裏には「任重道遠(任重くして道遠し)」という4つの字が現れました。私は隊を率いていましたから。

――文革期間、農村へ下放した後の経験についてお話いただけますか?
農村へ着いた後、私は小さな理想郷を築きました。生活を共にするグループには4人の男性と6人の女性、合わせて10人がいました。何が理想郷かと言うと、「能力に応じて働き、必要に応じて受け取る」ということです。これは共産主義の分配原則です。皆一緒に仕事をし、それぞれの労働点数を記録するのです。秋分を過ぎると、労働点数によって穀物や野菜を分けます。集団生活でしたので、手に入れた食材や現金は皆で一緒に使いました。必要な人が使うと言った具合でした。しかし、中には画家の男性がいて、多くの農民からオンドルの周りの壁に絵を描くよう頼まれ、沢山稼いで帰ってきました。私は彼には特殊な技能があり、他の人よりも多くのお金を稼いだのだから、それを(没収して)公有にするのは合理的でないと思いました。それから、分配原則に基づく共産主義制度は中止しました。
なぜこれほど多くの人が下放しなければならなかったのでしょうか?それは文革が都市の商工業をめちゃくちゃにしてしまったからです。学生は卒業後、仕事をする場所がありませんでしたが、農村はいずれにしても労働力を必要としており、それなら農村へ行こうということだったのです。何年か経ち、それぞれの都市の状況が回復すると、農村から再び知識青年を呼び戻しました。

この時、私の身分が問題になりました。他の人は戻りましたが、私は戻れなかったのです。なぜなら、私の父は台湾人で、母は日本人だったため、二重でスパイの嫌疑をかけられてしまったからです。戻ることはできなくても、私は焦りませんでした。元々農村に根を張り、革命しようと思っていたからです。その後、中央政府が台湾国籍の幹部を育成する政策を打ち出し、私が選ばれて、北京大学の入学枠をもらい、しかも日本語専攻だったのです。幸運なことに、私は大学で、日本語の文法を始めから最後まで体系的に学ぶことができたのです。
(卒業後)私は南海大学に行き、2年間日本語を教えました。日本語を教える際、日本語の高低アクセントを教えることができましたが、これは中国で初めてのことだったかもしれません。それまで教えた人はいませんでした。例えば、箸は「はし」(初めは高く、その後音が下がる)、箸は「はし」(初めは低く、その後音が上がる)というようなことです。私は北京大学にいたとき、金田一先生の辞典(三省堂国語辞典)を使っていて、一つ一つの単語に高低アクセントの印を付けました。当時、北京大学でこの事を教えている人はいませんでした。(私は辞書を使って自分で学びました。)南海大学で私が教えたクラスの学生の日本語は、日本人と似ています。

南海大学と神戸大学は姉妹校です。嬉しいことに、私は両校の青年教師相互研修プロジェクトに参加メンバーに選ばれました。しかしその後、中国側の経費不足で、プロジェクトが中止になったと知らされました。私は落胆し、父に日本に行くことができないか相談しました。父は東京にいる友人に連絡し、私の保証人になってもらうようお願いしてくれ、私は東京にやってきました。
来日後、大学の入試までまだ時間があったため、まず日本語学校に入りました。日本語を学びながらアルバイトで中国語を教えました。当時、私は上智大学にいました。日本の学生がクラブ活動に関心を持っているのを見て、7人の学生に声をかけ、中国語クラブの登録をしてもらいました。毎週土曜日の午後に空き教室を探し、日本人学生に中国語を教えました。多くの友達を作りたいと思ったからです。(夕方、近くレストランで)一緒に食事をしました。

――当時、佐々木さんは他の学生より少し年上でしたよね。
かなり年上でした。学校に入ったとき、私はもう31歳でしたが、他の学生は18歳になったばかりでした。その後、拓殖大学の中国語専攻の高田(高田勝巳)という学生が、上智大学に中国語クラブがあると聞いてやって来て、私たちは親友になりました。卒業を前に、彼が外務省の役人の友人を紹介してくれ、その方が私に野村證券から出向していた日中経済協会の方を紹介してくれました。そして、その出向員の方が私に野村證券の中国室を紹介してくれたのです。私は面接を経て、採用され、野村證券に入りました。中国には『大根が帰って来た』という童話がありますよね。ある人(うさぎ)が他人に大根をあげると、その人がまた違う人にあげ、最後には一周回って、また自分の手元に戻ってくるというお話です。私は中国語クラブを作り、色々経て、野村證券に入りました。(謝:友達付き合いは大切ですね。)
それから野村證券中国室の室長とよく知るようになってから、室長はなぜ私を採用してくれたのか話してくれました。室長は「私は清水寺の舞台から飛び降りるつもりでお前を採用した。(清水寺の舞台から断崖を飛び降りるように、命がけで私を採用したという意味)」と話しました。野村證券は日本で最も保守的な会社でしたので、それまで大陸出身の者を雇ったことがなかったのです。私が一人目でした。
室長が私を採用しようと思ったのは、私が信頼でき、誠実だったからです。室長が私に文革に対する考えを聞いた時、私はありのままに私は毛沢東の信奉者でしたから一生懸命やりましたと話しました。室長は私が文革が批判されていたのに追従して批判するようなことはしなかったのを見て、信頼できると思ったのでしょう。日本の会社はその人の能力よりも、その人が会社に忠誠を尽くすことができるかどうかを重視します。ですので、野村證券に入ったあとは二心なく、一途に会社に尽くしました。
日本の労働組合は他の国の労働組合と異なります。日本の労働組合は(全局的な考え方があり、)経営マネジメントをよく分かっているため、経営者によく協力します。経営者と給料を争い、高い給料を手にすれば会社は破産してしまうと知っているからです。ですので、日本の労働組合はデモ行進などをすることはありますが、経営者と決裂することはありません。
日本の会社における労働者間の競争は、中国とも異なります。他の人が成果を出したら、自分はその人よりもさらに良い成果を出そうとします。このような競争は結果的にプラス効果をもたらします。中国の労働者間の競争はどうでしょうか。よくあるのは何とかして他の人の足を引っ張ろうというやり方です。(結果的にマイナス効果となってしまいます。)
(日本人の最大の長所は絶対的多数の人が社会全体のために考えることです。)一つ典型的な例をお話ししましょう。日本の子どもが外に遊びに行くとき、母親は必ず「外出たら、人に迷惑をかけないでね。」と言います。中国の母親は何と言うでしょうか。「出かけたら損をしてはいけないよ。誰かに叩かれたら、叩き返さないといけないよ」と言います。根本的な考え方が明らかに異なるのです。

野村證券にいた時、最も感動したのはある顧客向けの総会でのことです。大きなホテルで(田淵)元社長が入り口に立ち、(若い人を含む)入ってくる顧客一人一人に90度の深いお辞儀をしていたのです。私は目を疑いました。中国では、たとえ小さな工場の工場長であっても、(人に接する態度は)とても偉そうにしているのを見たことがあったからです。その時、私はこれが「お客様は神様」ということであり、「市場経済」なのだと分かりました。会社の社長の地位がどんなに高かろうと、客よりは低い地位なのです。市場においては、常に買い手の地位が高いと言えるでしょう。もちろん、製品によって異なります。供給が需要に追い付かないような製品であれば、売り手の地位が高くなります。(とにかくその元社長の姿勢を目にして、)本当に勉強させていただき、私は在日中国人ビジネスマンの会や忘年会で、散会する時には来客の皆さんにお辞儀をし、「ありがとうございました」と言います。もし皆さんが参加してくれなかったら、私も何もすることができないからです。
――野村證券で働かれていた時のお話に戻りますが、当時主にどのようなお仕事に携われていたのでしょうか?
私が初め野村證券の中国室で何をしたのかと言いますと、野村證券が組織する投資訪問団で通訳をしました。その後、野村證券が野村中国投資株式会社という子会社を設立し、私はこの会社に転属しました。大きいプロジェクトは2つありました。1つは北京発展大厦(の建設)、もう一つはオークラガーデンホテル上海(の税務問題)でした。この北京発展大厦のために、私は2つ小さな貢献をしました。
初めて話し合いをした際のことですが、プロジェクトを開拓するときに、御存知の通り、日本人は中国人より慎重です。中国人はやると言ったらすぐやり始めますが、日本人は、まずしっかりと「試算」をします。中国語では「可行性研究」と言います。つまり1年目、2年目、3年目に、各年度どのくらいの収入でどのくらいの支出になるか、最終的に何年目に赤字から黒字に転じることができるのかなどを試算するのです。
当時中国側は試算をやろうとせず、「どうしてそんなに面倒くさい事をするのか。」と言うのです。私は野村中国投資株式会社の社長に「私が中国側に働きかけますので、経費をください。彼らに食事を招待します。」と言い、中国側の幹部たちを食事に招き、「プロジェクトが完成してすぐ破産してしまうことが多いなか、『慎重』こそがそれを避ける『保証』なんだ」と伝えました。こうしてようやく中国側を説得し、試算をしてくれることになりました。

北京発展大厦(の設立プロジェクトの成功)は、中国側の協力を得ることができ、そして私たちの会社の社長、当時は専務でしたが、その方の考え方がとても「日本人」的ではなかったことにも関係があります。日本人は協調性を重んじるので、中国側が何か意見を言えば、すぐに「はい、はい」と同意してしまいますが、その方は違い、最初から最後まで自分の意見を貫くのです。多くの共同出資企業がそうであるように、中国側が「中国側51%、日本側49%」と要求すると、彼は断り、「法律上は出資の割合を同じにしてもいいのです」と言って、最後はやはりそれぞれ50%の出資になりました。中国側は取引通貨を人民元にするよう要求しましたが、彼は譲らず、米ドルを使うよう要求したのです。結果、北京発展大厦は共同出資プロジェクトの中で、米ドルで取引したきわめて数少ない合弁会社の一つになりました。
(このプロジェクトで)日本側は中国側と細かく契約を話し合い、1年余りの時間をかけました。考え方がまったく異なる2つの国の人が契約を交わすというのは、非常に大変なことなのです。 契約条項のディティールまで、すべて私が翻訳しました。私の翻訳・通訳は、直訳しません。文字を訳すのではなく、双方の意図を完全に理解してからその意図をお互いに伝えるのです。こうすることで、双方はより良いコミュニケーションを取ることができるのです。
結果からみると、北京発展大厦のプロジェクトは、その年の中国と外国企業が共同投資を行うプロジェクトにおいて、予算通り完結した唯一のプロジェクトでした。予算を超えず、工期中に建設でき、経営開始後も双方の合作は非常に順調で、一度も言い争うことはありませんでした。北京発展大厦の契約文書は、北京の中外合弁プロジェクトのモデルになりました。(緻密なのですね。)そこには私の功労も少しありました。(笑)

――もう一つのプロジェクトは何でしたか?
もう一つはオークラガーデンホテル上海に関係しています。それに関して、私の最大の功績はオークラガーデンホテル上海が直面した不合理な費用徴収の問題を解決したことでしょう。当時、上海市が突然すべての外資系ホテルに対し、費用徴収を増やし、「旅行発展付加費」として、売上高の2%を徴収したのです。これは外資系ホテルに深刻なダメージを与えました。オークラガーデンホテルは収益が大きかったためまだ良かったのですが、その他のホテルは、私もいくつものホテルを訪ねましたが、日本航空のホテルなども、このままではダメだと言っていました。

私は上海の旅行局と話し合い、この「付加費」を取り消すことができないか聞きました。彼らはずいぶんと話した後に、これは市が決めたものだから、私たちはどうしようもないと言いました。それで私が北京の方に行って解決をお願いしていいかと聞くと、彼らはいいと答えたのです。私は中国語で上海政府を訴える申立書を書き、専務にサインをもらい、それを持って北京へ行きました。しかしその時どこに意見を述べたらいいかわかりませんでした。その後、経済貿易部でしょうか、ある部門が開催したセミナーに参加し、そこで不正徴収の問題、そして国務院のどの部門が対処しているのかについて言及しました。それから、私は国務院のこの部門のもとへ行きました。たしか「不合理な徴収を取り締まるチーム」というような名前だったかと思います。当時地方政府の企業に対する過度な費用徴収はあまりにも多く、上海(の外資系ホテル)はそのうちの一つに過ぎませんでした。
私が(国務院の)建物の中に入ろうとしたとき、解放軍が外で見張っていました。もし私が日本国籍だと言えば、絶対に入れさせてもらえなかったので、私は「事務室の誰々に大事な用がある」と言い、その解放軍は私の流暢な中国語を聞いて、何も思わずに私を中に入れたのです。入ってみると、国務院の方は非常に親切で、すぐに「丁度よい!」と言いました。その方は丁度「不正徴収撤廃リスト」を作っていて、私が話した「付加費」の件を撤廃リストの中に入れてくれたのです。タイミングがあまりにもよかったのです!

それから、ホテルニューオークラに来てから、2つのことをやりました。
1つは 大倉集古館に関することです。大倉集古館は日本で最初の(財団法人の)私立美術館で、3万冊の中国宋元明清時代の書物を収蔵していました。
中国の大陸の古い書物の多くは文革で焼かれてしまい、保存されているものは多くありません。大倉集古館の書物は非常に価値が高く、手を施して保存し、定期的に消毒、殺菌を行っていました。私が聞いたのは、ある時期になると、(菌を)殺した後に毒を撒いてネズミを殺すため、もしその時中に入ってしまったら死んでしまうということでした。これらの書物は100年間保存されていたのです。当時、北京大学の教授が見に来た時には「日本人がこれほどしっかりと保存しているとは。元のままの状態で保存されているじゃないか。」と非常に驚かれていました。
ホテルニューオークラの文化財団の理事長から、「北京大学が買い取りたいと言っているが、売るべきだろうか?」と聞かれました。私が「北京大学は日本で言う東京大学のような影響力があり、東京大学よりもさらに影響力があります。北京大学は文化面だけでなく、政治においても影響があるからです。」と話すと、理事長は嬉しそうにして、北京大学に売ることを決めたのです。
契約書の作成は私が担当しました。3万冊の中に、3冊日本が国宝に定めたものがありました。うち1冊は西遊記の最古のテキスト(『新刻出像官板大字西遊記』(世徳堂本))でしたから、売ることは許されませんでした。3つの国宝と9つの美術品合わせて12点は売りませんでしたが、他の3万点あまりは全て売りました。

あともう一つ、記念碑があります。中国同盟会発祥の地です。
中国同盟会はここ(ホテルニューオークラ)で設立しました。ホテルニューオークラの創始者は大倉喜七郎といいます。喜七郎の父は喜八郎で、日本十大財閥の一つでした。財閥で家が大きかったので、孫中山が同盟会の結成大会を開く時に彼らの家の大部屋を使い、100人余りが集いました。大倉喜八郎は孫中山に300万円の融資をしました。ですので、大倉喜八郎は中国の辛亥革命を大いに支援した日本人の一人と言えるでしょう。
この記念碑が建てられた経緯についてお話ししましょう。十数年前、辛亥革命の100周年記念の際に日本側が記念大会を開催し、私は参加しました。その際、日本女子大学の久保田教授がいらっしゃり、私たちが名刺交換をする時に、久保田先生は「大倉」の文字を見て、私に「中国同盟会は君たちのところで設立したのだから、そちらに記念碑を立てないと。」とおっしゃったのです。

確かにそうだと思い、私は久保田教授にホテルニューオークラの社長に手紙を書き、この記念碑を建てる理由を話してくれないかと相談しました。久保田教授がどのように考察、鑑定したのか、どのように中日双方の学界の認定を経て、ここを中国同盟会発祥の地として確認できたかを書いてもらいました。その一連の資料を送ってもらいました。
私は意義が非常に大きいと思いました。中華民国はアジアで初めての共和国であり、孫中山が日本人の支援を受けて設立した国です。その意義はどれだけ大きいのでしょうか?これは近代史における日中友好の起点とも言えるでしょう。

――中日貿易関係において重要な貢献をされてきた佐々木さんの立場から、今後中日間ではどのような方面で努力したり、新たな試みを行っていったりすることができると思いますか?
もちろん、最も大切な協力、友好的な協力は経済上のものでしょう。ところが、大企業は、元々のやり方を今も続けており、変化はそれほど大きくありません。中小企業は撤退し始めています。現在日本から引き上げる企業も少なくありません。もちろん一部の企業が撤退しても大きな影響はありません。中国の企業も発展し、古いものから新しいものに代わり、技術的にも優れたものになってきたからです。しかし元々中国にいた日本企業が後れを取り始めています。一部企業はその重圧に迫られ撤退しているのです。
――佐々木さんの日中の比較のお話はとても興味深いです。日本に来たばかりの時、中国と日本の大きな違いを感じたところは何ですか?
私が日本に来たばかりの時に感じた最も大きな違いは、街の通りが中国よりきれいであるということです。2つ目に電車の広告が多いこと、3つ目に日本人は歩くのが速く、皆仕事が忙しいことです。最も壮観だったのは、朝起きて駅へ歩いていく時、駅からまるで洪水のように人が出て来て、皆慌ただしく出勤していた光景でした。これが経済発展した国の一面で、経済発展とは労働者が忙しいことを意味するのだとのだと感じました。中国のようにゆったりとしていませんでした。私が中国に居たときには「8時は出社時間、着くのは9時。着いたらお茶を飲み、新聞を読む。」という言葉が流行っていました、先に新聞を読んだりして、急いで仕事をしないのです。ただ、今はもう異なり、中国にも日本のように忙しい会社がいくつもあり、ファーウェイは日本の会社よりもさらに忙しいです。
――最後に読者の皆さんに中国語と日本語の学習の心得をお話していただけますか?
中国語と日本語は、同文同種という言い方もありますが、2つのまったく関係のない言語だと思います。特に文法については、英語と比較してみると、日本語と英語の文法は違いがさらに大きいです。
日本語は中国語と同じように、名詞を修飾する際に、基本的に連体修飾語が名詞の前にあります。英語は多くの場合フレーズが名詞を修飾するので、後ろに持って行く傾向がある(フレーズが後ろから名詞を修飾する)のです。中国語の文法は、「動詞+名詞」ですから、英語とほとんど変わりません。しかし話をするときには、連体修飾語を使って1つの単語を説明することが多いので、感覚的には中国語は日本語により近いように思います。
中国語には四声があると言われますが、私の個人的な研究では、7つの声調があると考えています。半三声と三声は異なり、軽声にも高軽声と低軽声の2種類があります。日本語には四声がないと言いますが、私は日本語にも四声があると思います。例を挙げましょう。「唐招提寺」―「とう」は中国語の二声、「しょう」は中国語の一声、「だい」は中国語の四声、「じ」は中国語の軽声で、「とうしょうだいじ」は「二声・一声・四声・軽声」となり、中国語の「明天去吧」とまったく同じなのです。また、何か間違えてしまったとき、日本語では「あ〜、また失敗した」と言いますが、この「あ〜」は三声です。
中国語は日本の民間で人気があります。もし信じられなければ、横浜中華学校を見てみてください。(学生は)超満員です。政府の関係は良くありませんが、日本にとって最も大切な外国語は英語でなく中国語だと、日本人は心の中でわかっているのです。ですので、将来日本で中国語を学ぶ人は必ず増えると思います。皆さん頑張ってください!

佐々木芳邦氏
• 中国金融研究会 会長
• 在日中国人ビジネスマンの会 会長
• 元北京大学日本校友会会長
1950年2月6日 東京生まれ。(父親台湾出身、母親秋田出身)
1953年7月 多数の日本華僑と共に中国天津へ渡る。
1966年6月 中学校3年生卒業時始まった文化大革命に参加。後ある学校の先生と共に新聞 「紅鋒」を創刊。
1968年10月 学生400名を率い内モンゴルの農村へ「下放」、農業に従事。
1973年10月 北京大学日本語学科入学
1976年9月 内モンゴル科学技術情報研究所入社
1978年10月 南開大学日本語教育室へ転職、講師に
1980年7月 留学に日本へ渡り、日米会話学院日本語学科入学。
1981年4月 上智大学経営学科入学
1985 野村證券株式会社中国室入社
1988 グループ会社野村・中国投資株式会社へ出向
2010 野村・中国投資株式会社を退職
2010 ホテルオークラ事業本部へ就職
2020 ホテルオークラ管理本部退職
2021 TEN法律事務所顧問就任
2024 徳恒法律事務所東京オフィス顧問就任
今回のインタビュー内容は月刊中国語学習誌『聴く中国語』2024年8月号と9月号に掲載されています。さらに詳しくチェックしてみたい方は、ぜひ『聴く中国語』2024年8月号、『聴く中国語』2024年9月号をご覧ください。


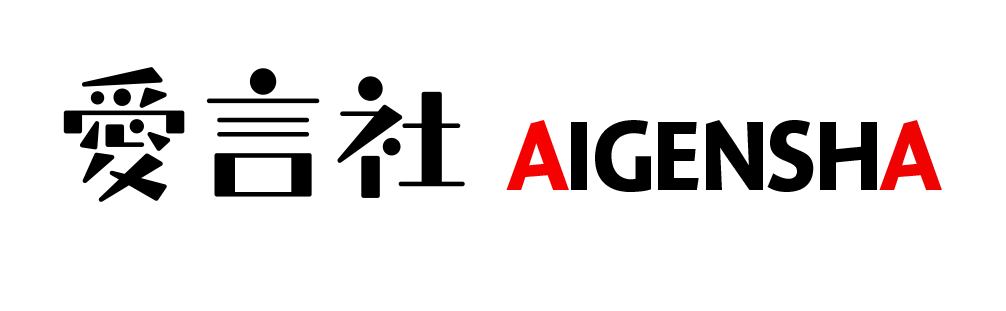



コメント