昨年11月、「香港映画祭」と「東京国際映画祭」が東京で開催されました。今回は両映画祭で上映された、話題の香港映画『ラスト・ダンス(原題:破・地獄)』をご紹介します。

映画の舞台は、アフターコロナの香港。パンデミックの影響で、ブライダル業から葬儀社へ転身した主人公ダオシェン。彼は法事を担当する道士(道教の儀礼を執り行う専門家)のマンと衝突しながらも、葬儀を行う意義、そして生と死について理解を深めていきます。
ダオシェン役にはダヨ・ウォン、マン役にはマイケル・ホイ。香港でコメディ俳優として知られるふたりの共演は、実に約32年ぶり。上映前から話題性抜群で、公開後には香港の歴代興行収入ランキング1位に輝く大ヒット作となりました。

物語の大きなテーマとなるのは、マンが葬儀で魅せる道教の伝統儀式「破地獄」です。主に早世者や自殺者の葬儀で、故人を地獄から解き放つため行う儀式。香港の無形文化遺産に登録されています。
儀式の起源は仏伝故事『目連救母』で、劇中でも葬儀に参列する幼児が、この逸話の絵本を読むシーンが登場します。『目連救母』はお釈迦様の弟子目連が、地獄に堕ちた母親を救う物語。目連が救済のために九つの地獄の門を破った逸話から、「破地獄」では火が付いた盆を地獄に見立て、道士のマンがその周囲に並べた九枚の瓦を剣で割ります。
故人のために地獄の門をたたき破るマン。剣を片手に、踊るように瓦を割る様は美しく、儀式はまさしく故人へ向けた「最後の舞い」です。

こうして、映画では「破地獄」を美しく映しつつも、道教に残る時代錯誤な「女人禁制」の風習の残酷さも浮き彫りにします。
死者を救うマンとは対照的に、娘マンユッ(ミシェール・ワイ演)は消防署の救護員として、生きている人を救う仕事をしています。職場では男性顔負けと称賛される一方で、家庭内では女性であることから、「穢れ」を持つものとして父親のマンに道士の仕事から遠ざけられています。道士に憧れる彼女にとって、儀式「破地獄」は劣等感を抱かせる象徴。
しかし、物語のクライマックスで披露される「破地獄」は、道教の風習によって生じた父と娘の確執を砕き、悪しき風習へのアンチテーゼとして姿を変えます。

香港版『おくりびと』(2008・日本)とも称される本作は、生死の狭間に立たされた人を救う者たちを軽妙かつ繊細に描いてます。死の淵に立つ命を救う救護士のマンユッ。遺族の心を救う葬儀社のダオシェン。そして死者の魂を救う道士のマン。 実は、それぞれが暗い過去を抱え、生きながらにして「地獄」の中にいます。しかし儀式「破地獄」を通して人生を見つめなおし、「地獄」から抜け出していきます。
映画では黄泉に生きる者を苦しみから救う儀式が、現世に生きる者の地獄をも打ち砕いてくれるのです。

一口メモ:
道教は仏教の考えを伝来とともに吸収したため、仏伝故事『目連救母』も教えの一つとして語られています。ただ、二つの宗教では目連の救出方法は異なります。仏教では目連が現世で善行を行い、間接的に母を救うのに対し、道教では法具を使って直接母を救います。
話題となった中国映画『西湖畔に生きる(草木人間)』(2023)は現代版『目連救母』と称されていますが、参考にしているストーリーはいわば仏教版。その違いに注目して2作をみてみるのも面白いかもしれません。
西木南瓜(さいき かぼちゃ)
SNSクリエイター・コラムニスト。名古屋在住。アジアの映画をこよなく愛する影迷(映画ファン)。上海外国語大学修士課程修了後、中国語講師を経て映画公式SNSの運用代行や宣伝企画、広告プランニングなどで活動中。
今回紹介したコラムは『聴く中国語』2025年3月号に掲載しております。

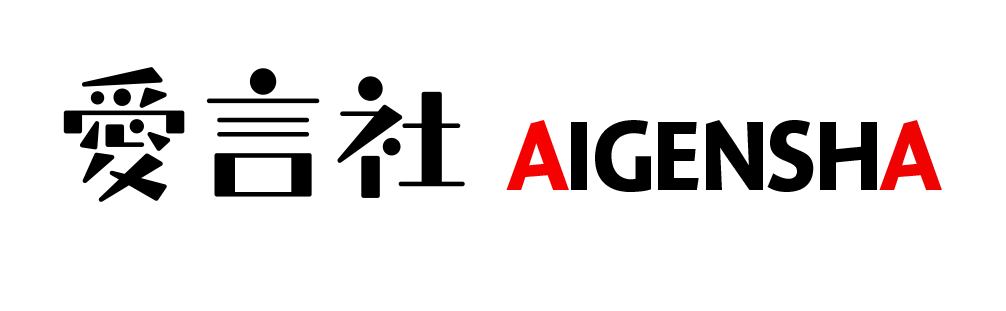



コメント